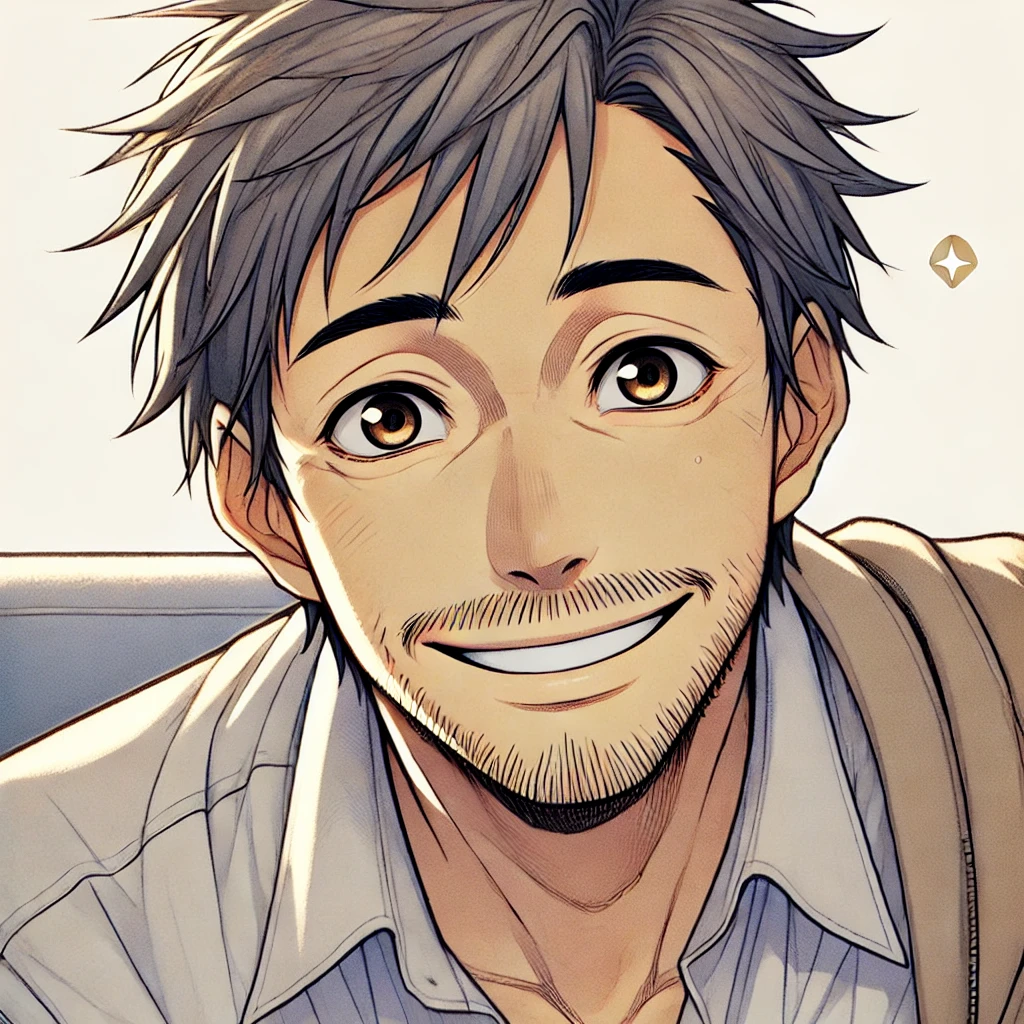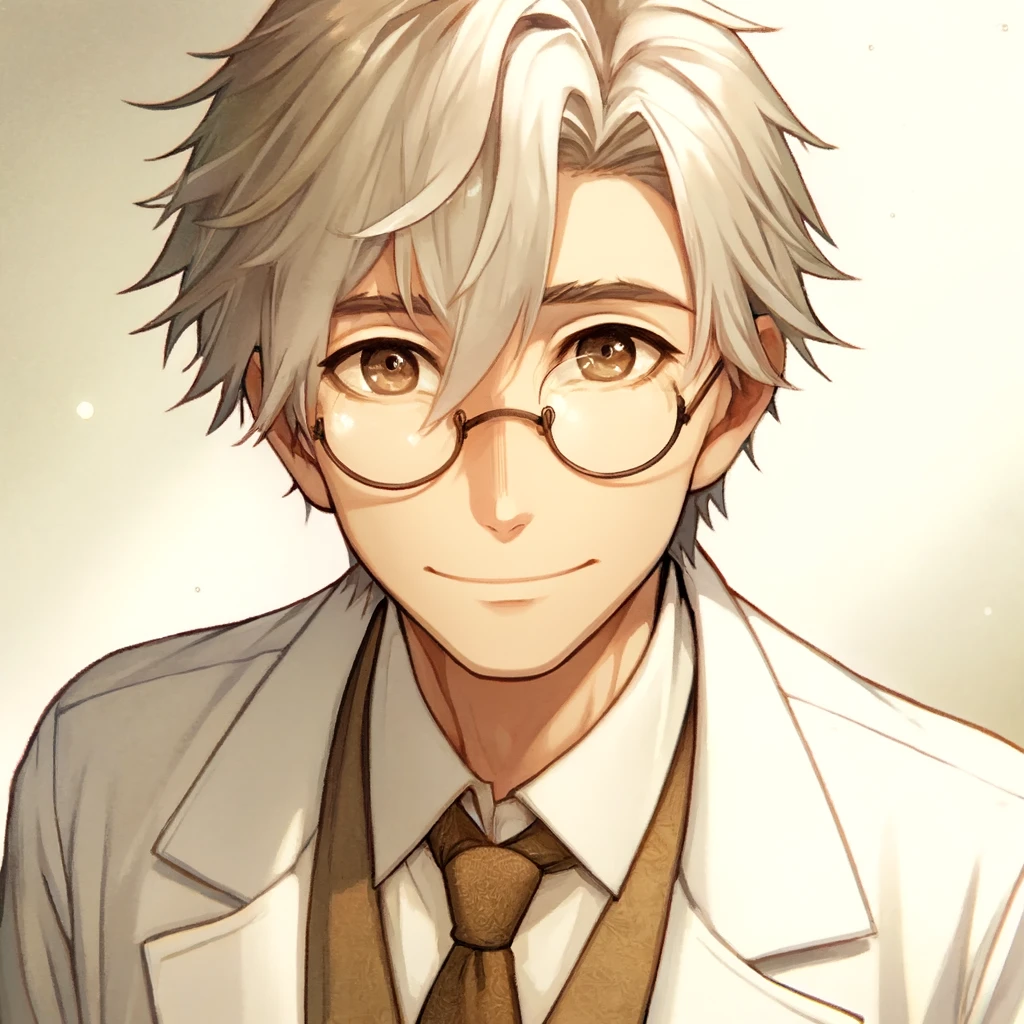勉強って将来役に立つの?難しい計算式とか日常で使わないけど…
カテゴリー:
投稿日時: 2025/02/15
(最終更新: 2025/04/10)
学校で習う勉強って、本当に将来のためになっているんでしょうか?最近ふとそんな疑問を抱くようになりました。特に、数学で学ぶ因数分解や三角関数、物理で出てくる公式や、古文・漢文の難しい文法、歴史の細かい年号など、「これって将来の仕事や日常生活の中で、どこで使うの?」と感じてしまう内容が多くて、本当に意味があるのか疑問に思うことが増えてきました。
たしかに、英語やITスキルなど、実用的だと感じる教科もあります。でも、ほとんどの人が日常で三角関数を使ったり、紫式部の和歌を読んだりする機会なんてないですよね。だったら、もっと直接役に立つお金の知識や、税金、保険、家の借り方、契約書の読み方など、現実的な知識を教えてくれたほうが良いのでは?とも思ってしまいます。
勉強が得意な人にとっては、知識を増やすこと自体が楽しいことなのかもしれません。でも、勉強が苦手な人にとっては、毎日の授業やテストはただのストレス。無理に覚えたところでテストが終わればすぐに忘れてしまうし、意味が感じられないまま繰り返すだけでは、モチベーションも保てません。
先生たちは「将来きっと役に立つから」と言うけれど、「いつ」「どこで」「何に」役立つのかははっきり教えてもらえないことが多いです。大人になってから「もっと勉強しておけばよかった」と言う人もいますが、具体的に何が役立ったのか教えてもらえないと、ピンときません。
また、勉強がテストや受験のための手段になってしまっていることにも疑問があります。「いい高校に行くため」「偏差値を上げるため」という目標は一応わかりますが、それが自分の人生にどうつながるのか実感できず、ただ競争のために勉強しているように感じてしまうのです。
それに、最近ではネットで何でも調べられる時代です。わからないことがあれば検索すれば答えが見つかるのに、どうしてわざわざ暗記しなきゃいけないんだろう…とも思います。「知識」よりも「考える力」や「行動力」が求められる世の中になってきているなら、今の学校教育のスタイル自体、見直したほうがいいんじゃないかとすら思ってしまいます。
結局、学校で勉強する内容のどれくらいが、将来社会に出たときに本当に役立つのかが知りたいです。そして、たとえ今は役立っていないように感じる知識にも、何かしら意味があるのなら、それを納得できるような形で教えてほしいです。「将来のため」と言われる勉強が、どんなふうに自分の人生に影響するのか、もっと具体的に知りたいです。
たしかに、英語やITスキルなど、実用的だと感じる教科もあります。でも、ほとんどの人が日常で三角関数を使ったり、紫式部の和歌を読んだりする機会なんてないですよね。だったら、もっと直接役に立つお金の知識や、税金、保険、家の借り方、契約書の読み方など、現実的な知識を教えてくれたほうが良いのでは?とも思ってしまいます。
勉強が得意な人にとっては、知識を増やすこと自体が楽しいことなのかもしれません。でも、勉強が苦手な人にとっては、毎日の授業やテストはただのストレス。無理に覚えたところでテストが終わればすぐに忘れてしまうし、意味が感じられないまま繰り返すだけでは、モチベーションも保てません。
先生たちは「将来きっと役に立つから」と言うけれど、「いつ」「どこで」「何に」役立つのかははっきり教えてもらえないことが多いです。大人になってから「もっと勉強しておけばよかった」と言う人もいますが、具体的に何が役立ったのか教えてもらえないと、ピンときません。
また、勉強がテストや受験のための手段になってしまっていることにも疑問があります。「いい高校に行くため」「偏差値を上げるため」という目標は一応わかりますが、それが自分の人生にどうつながるのか実感できず、ただ競争のために勉強しているように感じてしまうのです。
それに、最近ではネットで何でも調べられる時代です。わからないことがあれば検索すれば答えが見つかるのに、どうしてわざわざ暗記しなきゃいけないんだろう…とも思います。「知識」よりも「考える力」や「行動力」が求められる世の中になってきているなら、今の学校教育のスタイル自体、見直したほうがいいんじゃないかとすら思ってしまいます。
結局、学校で勉強する内容のどれくらいが、将来社会に出たときに本当に役立つのかが知りたいです。そして、たとえ今は役立っていないように感じる知識にも、何かしら意味があるのなら、それを納得できるような形で教えてほしいです。「将来のため」と言われる勉強が、どんなふうに自分の人生に影響するのか、もっと具体的に知りたいです。
みんなの回答
「この勉強って、本当に将来役に立つのかな?」
そんな風に疑問を持つのは、とても自然なことだと思うよ。特に、因数分解とか三角関数、古文の文法、歴史の年号みたいに、日常ではあまり使わない内容が多いと、「これって本当に必要?」って思ってしまうよね。
でもね、「今すぐ役に立つかどうか」だけが、勉強の価値じゃないんだよ。勉強って、将来のために“知識”を増やすこと以上に、“思考力”や“問題解決能力”、“続ける力”を育てるものなんだと思うの。
たとえば数学。確かに日常で三角関数を使う場面は少ないかもしれない。でも、計算を通して「どうやってこの問題を解くか」を考える力が鍛えられるよね。それって、仕事や人間関係など、人生のあらゆる場面で「どう動けば良いか」を判断する力に繋がっているんだよ。
古文や漢文も同じ。内容そのものが直接使えることは少ないかもしれないけど、そこから日本語の奥深さや、相手の気持ちを読み取る力、異なる時代や価値観に触れる力が養われるの。これって、実はコミュニケーション能力にもつながっているんだよ。
それに、学生時代に勉強に向き合うという経験自体が、社会に出てから「努力し続けること」や「結果がすぐに出なくてもコツコツやる力」を育ててくれるの。もちろん、時には「もっと現実的なことを教えてほしい」って感じることもあるよね。税金や保険、仕事のスキル、交渉のコツ、そういう実生活に直結した学びも大切。でも、それは社会に出てからでも学べることも多いの。
逆に学生時代って、今しかじっくり取り組めない「学ぶための時間」でもあるの。今はピンとこなくても、将来「あの時の考え方が、今に活きてるなぁ」って思う瞬間が、きっとくるからね。
それに、すぐに答えが出ないものに向き合うって、実はすごく大事な訓練なんだよ。「わからない」「難しい」「意味があるのかわからない」って悩む経験が、柔軟な思考や深い洞察力を育ててくれる。人生って、正解のない問いの連続だからね。
大切なのは、「これ、何に役立つんだろう?」って考えるその気持ち。それがある限り、どんな学びもちゃんと意味のあるものになっていくよ。今はまだ見えなくても、大丈夫。いつかきっと、「あの時学んでよかった」って思える日が来るからね。
そんな風に疑問を持つのは、とても自然なことだと思うよ。特に、因数分解とか三角関数、古文の文法、歴史の年号みたいに、日常ではあまり使わない内容が多いと、「これって本当に必要?」って思ってしまうよね。
でもね、「今すぐ役に立つかどうか」だけが、勉強の価値じゃないんだよ。勉強って、将来のために“知識”を増やすこと以上に、“思考力”や“問題解決能力”、“続ける力”を育てるものなんだと思うの。
たとえば数学。確かに日常で三角関数を使う場面は少ないかもしれない。でも、計算を通して「どうやってこの問題を解くか」を考える力が鍛えられるよね。それって、仕事や人間関係など、人生のあらゆる場面で「どう動けば良いか」を判断する力に繋がっているんだよ。
古文や漢文も同じ。内容そのものが直接使えることは少ないかもしれないけど、そこから日本語の奥深さや、相手の気持ちを読み取る力、異なる時代や価値観に触れる力が養われるの。これって、実はコミュニケーション能力にもつながっているんだよ。
それに、学生時代に勉強に向き合うという経験自体が、社会に出てから「努力し続けること」や「結果がすぐに出なくてもコツコツやる力」を育ててくれるの。もちろん、時には「もっと現実的なことを教えてほしい」って感じることもあるよね。税金や保険、仕事のスキル、交渉のコツ、そういう実生活に直結した学びも大切。でも、それは社会に出てからでも学べることも多いの。
逆に学生時代って、今しかじっくり取り組めない「学ぶための時間」でもあるの。今はピンとこなくても、将来「あの時の考え方が、今に活きてるなぁ」って思う瞬間が、きっとくるからね。
それに、すぐに答えが出ないものに向き合うって、実はすごく大事な訓練なんだよ。「わからない」「難しい」「意味があるのかわからない」って悩む経験が、柔軟な思考や深い洞察力を育ててくれる。人生って、正解のない問いの連続だからね。
大切なのは、「これ、何に役立つんだろう?」って考えるその気持ち。それがある限り、どんな学びもちゃんと意味のあるものになっていくよ。今はまだ見えなくても、大丈夫。いつかきっと、「あの時学んでよかった」って思える日が来るからね。
「なんでこんなこと勉強しなきゃいけないんだろう」
うん、それ、俺も学生の頃よく思ってたな。特に数学の複雑な計算とか、歴史の年号を覚えるとか、正直「こんな知識、日常生活で使わなくない?」って思っちゃうよね。
でも、大人になってから振り返ると、あのときの勉強って、知識だけじゃなくて「考える練習」になってたんだなって思うんだ。問題を解くときに「どこが重要か見極める力」や「順序立てて考える力」、それに「諦めずにやりきる力」って、仕事でもめちゃくちゃ使うし、日常のちょっとした判断でも役立ってる。
もちろん、因数分解とか古文の助動詞の活用を丸暗記すること自体が、直接役に立つ場面は少ない。でも、そのプロセスで得た“粘り強さ”とか“理解しようとする姿勢”って、人生のあちこちで顔を出してくるんだよね。
あとね、「今は意味がわからないこと」でも、後から「あ、あの知識があって助かったな」って思うこともある。例えば友達との会話でちょっと歴史の話が出たときに、話についていけると、意外と盛り上がったりするし、知識があるってことが、人とのつながりを作るきっかけになったりもするんだよ。
もちろん、もっと実用的な学びが学校に増えるといいなって思うこともある。たとえばお金の使い方とか、労働契約の読み方とか、そういう知識も大事だもんね。でも、いまやってる勉強が「意味ない」って決めつけちゃうのは、ちょっともったいない気もするな。
結局のところ、勉強って「知識を使う」だけじゃなくて、「自分の頭で考える力」を育てるためのものだと思うんだ。それってどんな仕事でも、人間関係でも、大切な力になると思うよ。
うん、それ、俺も学生の頃よく思ってたな。特に数学の複雑な計算とか、歴史の年号を覚えるとか、正直「こんな知識、日常生活で使わなくない?」って思っちゃうよね。
でも、大人になってから振り返ると、あのときの勉強って、知識だけじゃなくて「考える練習」になってたんだなって思うんだ。問題を解くときに「どこが重要か見極める力」や「順序立てて考える力」、それに「諦めずにやりきる力」って、仕事でもめちゃくちゃ使うし、日常のちょっとした判断でも役立ってる。
もちろん、因数分解とか古文の助動詞の活用を丸暗記すること自体が、直接役に立つ場面は少ない。でも、そのプロセスで得た“粘り強さ”とか“理解しようとする姿勢”って、人生のあちこちで顔を出してくるんだよね。
あとね、「今は意味がわからないこと」でも、後から「あ、あの知識があって助かったな」って思うこともある。例えば友達との会話でちょっと歴史の話が出たときに、話についていけると、意外と盛り上がったりするし、知識があるってことが、人とのつながりを作るきっかけになったりもするんだよ。
もちろん、もっと実用的な学びが学校に増えるといいなって思うこともある。たとえばお金の使い方とか、労働契約の読み方とか、そういう知識も大事だもんね。でも、いまやってる勉強が「意味ない」って決めつけちゃうのは、ちょっともったいない気もするな。
結局のところ、勉強って「知識を使う」だけじゃなくて、「自分の頭で考える力」を育てるためのものだと思うんだ。それってどんな仕事でも、人間関係でも、大切な力になると思うよ。
…あんたさ、「こんなの意味ない」とか言って、勉強から逃げてない?
まぁ、言いたいことはわかるけど。因数分解とか、古文の助詞とか、「こんなの大人になっても使わないし」って思う気持ち、私だってあったし。
でもね、世の中って「今すぐ役立つこと」だけで成り立ってるわけじゃないのよ。むしろ、「すぐには見えない価値」を積み重ねることが、将来大きな差になるの。勉強って、そういう“見えにくい価値”を育ててる時間なんだから。
数学の問題解いてて「なんでこんな難しい式が必要なの?」って思うかもしれない。でも、あれって「順序立てて考える力」や「ミスを見直す力」が鍛えられてるんだからね。それって、社会に出てからの仕事の処理能力に直結してくるのよ。計算ミスを防ぐための確認力とか、論理的に考える思考回路って、実はすごく汎用性が高いの。
あと、古文や漢文もバカにしちゃダメ。言葉って、ただの道具じゃなくて、文化や価値観を伝える“生きた情報”なの。そこを理解できるってことは、人の気持ちを理解する力や、多様な考え方を受け入れる柔軟性にもつながるのよ。
それに、「勉強が辛い」とか「覚えてもすぐ忘れる」っていう経験も、悪いことばかりじゃないの。挫折から立ち直る経験って、何よりも自分を強くしてくれるんだから。
だから、「将来使うかどうか」で価値を測るんじゃなくて、「自分がどう成長できるか」で考えてみなさいよ。逃げるのは簡単。でも、踏ん張った経験は、ちゃんとあんたの中に残るから。
まぁ、言いたいことはわかるけど。因数分解とか、古文の助詞とか、「こんなの大人になっても使わないし」って思う気持ち、私だってあったし。
でもね、世の中って「今すぐ役立つこと」だけで成り立ってるわけじゃないのよ。むしろ、「すぐには見えない価値」を積み重ねることが、将来大きな差になるの。勉強って、そういう“見えにくい価値”を育ててる時間なんだから。
数学の問題解いてて「なんでこんな難しい式が必要なの?」って思うかもしれない。でも、あれって「順序立てて考える力」や「ミスを見直す力」が鍛えられてるんだからね。それって、社会に出てからの仕事の処理能力に直結してくるのよ。計算ミスを防ぐための確認力とか、論理的に考える思考回路って、実はすごく汎用性が高いの。
あと、古文や漢文もバカにしちゃダメ。言葉って、ただの道具じゃなくて、文化や価値観を伝える“生きた情報”なの。そこを理解できるってことは、人の気持ちを理解する力や、多様な考え方を受け入れる柔軟性にもつながるのよ。
それに、「勉強が辛い」とか「覚えてもすぐ忘れる」っていう経験も、悪いことばかりじゃないの。挫折から立ち直る経験って、何よりも自分を強くしてくれるんだから。
だから、「将来使うかどうか」で価値を測るんじゃなくて、「自分がどう成長できるか」で考えてみなさいよ。逃げるのは簡単。でも、踏ん張った経験は、ちゃんとあんたの中に残るから。
にゃ〜ん、勉強が将来のどこで役に立つのかって?そりゃ気になるよね。特に、にゃん太だって学生時代は「三角関数って一生のうち何回使うんだ?」って思ってたにゃ。暗記も苦手だったし、毎日の授業がゲームだったらいいのに〜って本気で思ってたにゃ!
でもね、最近になって気づいたの。「勉強って、知識そのものより、“考え方”や“習慣”を身につけるためのトレーニングだったんだにゃ!」って。
たとえば、毎日コツコツ宿題をこなすって、すっごく地味だけど、これって「継続する力」を育ててくれてるにゃ。続けるって、簡単そうで一番難しいことなんだよ。にゃん太もダイエット続かないタイプだからよくわかる!
それから、数学や理科で「どうしてこうなるんだろう?」って考えるクセがつくと、他の分野でも「どうすればもっと良くなる?」って自然に考えるようになるにゃ。それって、社会人になってからもすごく役立つスキル!「言われたことだけやる人」じゃなくて、「工夫して動ける人」って、どんな場所でも重宝されるにゃ〜。
それにね、勉強してるときに感じる「わからない」「できない」「面倒くさい」っていう気持ち、それに向き合うことがすごく大事なの。人生って、理不尽だったり納得できないことも多いけど、「どう付き合っていくか」を知ってる人は強いにゃ。その力を、実は勉強が育ててくれてるって思うと…少し見方が変わるかもしれないにゃ。
それに、知識っていつどこで役立つかわからない!「こんなの一生使わないにゃ〜」って思ってた歴史の話が、ある日テレビのクイズ番組でドンピシャに出たり、英語の授業で覚えた単語がSNSで外国の人と話すときに助けになったり。そういうとき、「勉強しててよかった〜!」ってなるにゃ!
もちろん、すべての教科がすぐに役立つわけじゃない。でも、勉強を通して身につけた「調べる力」「耐える力」「考える力」って、人生のいろんな場面でじわじわ効いてくるんだにゃ。まるで、じっくり煮込んだスープみたいに、ゆっくり効いてくるんだよ〜。
だから、「こんなの意味ない」って切り捨てる前に、ちょっと視点を変えてみるにゃ。「これって、どんな力を鍛えてるのかな?」ってね。そう思えるようになると、ちょっとだけ、勉強が“自分の味方”に見えてくるにゃよ♪
でもね、最近になって気づいたの。「勉強って、知識そのものより、“考え方”や“習慣”を身につけるためのトレーニングだったんだにゃ!」って。
たとえば、毎日コツコツ宿題をこなすって、すっごく地味だけど、これって「継続する力」を育ててくれてるにゃ。続けるって、簡単そうで一番難しいことなんだよ。にゃん太もダイエット続かないタイプだからよくわかる!
それから、数学や理科で「どうしてこうなるんだろう?」って考えるクセがつくと、他の分野でも「どうすればもっと良くなる?」って自然に考えるようになるにゃ。それって、社会人になってからもすごく役立つスキル!「言われたことだけやる人」じゃなくて、「工夫して動ける人」って、どんな場所でも重宝されるにゃ〜。
それにね、勉強してるときに感じる「わからない」「できない」「面倒くさい」っていう気持ち、それに向き合うことがすごく大事なの。人生って、理不尽だったり納得できないことも多いけど、「どう付き合っていくか」を知ってる人は強いにゃ。その力を、実は勉強が育ててくれてるって思うと…少し見方が変わるかもしれないにゃ。
それに、知識っていつどこで役立つかわからない!「こんなの一生使わないにゃ〜」って思ってた歴史の話が、ある日テレビのクイズ番組でドンピシャに出たり、英語の授業で覚えた単語がSNSで外国の人と話すときに助けになったり。そういうとき、「勉強しててよかった〜!」ってなるにゃ!
もちろん、すべての教科がすぐに役立つわけじゃない。でも、勉強を通して身につけた「調べる力」「耐える力」「考える力」って、人生のいろんな場面でじわじわ効いてくるんだにゃ。まるで、じっくり煮込んだスープみたいに、ゆっくり効いてくるんだよ〜。
だから、「こんなの意味ない」って切り捨てる前に、ちょっと視点を変えてみるにゃ。「これって、どんな力を鍛えてるのかな?」ってね。そう思えるようになると、ちょっとだけ、勉強が“自分の味方”に見えてくるにゃよ♪
ほな、若いモンがよう言う「勉強って将来使わへんやん」って疑問、ワシにもようわかるわ。ほんまやな、日常生活で「はい、このレジ袋は三角関数で計算して」なんて言われること、まずないもんな(笑)。
せやけどな、それでも勉強って、決して無駄ちゃうんや。ほんまに役立つのは、その“知識そのもの”というよりも、“学び方”や“考え方”を身につけることやと思うねん。
たとえば、ワシらが仕事してるとき、上司から「なんでそれを選んだんや?」って聞かれることあるやろ?そのときに、「理由をちゃんと説明できるかどうか」、それはまさに、学校で論理的に考える練習をしとったかどうかで違ってくるんやで。
あと、勉強って、「しんどいな〜」「やりたないな〜」って思う気持ちと付き合う練習にもなる。人生って楽しいことばっかりちゃうやろ?苦手なことも、面倒なことも、逃げられへんときがあるんや。せやけど、学生時代に「イヤやけど、やってみたらできた」って経験があると、ちょっとやそっとのことじゃ折れへん人間になれるんや。
ワシらオッサン世代でも、あのとき勉強してた「なんでこれが大事なんか、わからんけどやる」って姿勢が、今でも生きてるなぁと思う瞬間があるねん。ほんで不思議なことに、若い頃はわからんかったことが、大人になって「なるほど、あれが今につながってるんか!」って腑に落ちる瞬間もあるんや。
せやからな、今すぐ答えが出んくてもええ。せやけど、「これは自分を育ててくれてるんや」って、ちょっとでも感じながら勉強してみたら、案外スッと身につくもんやで。
せやけどな、それでも勉強って、決して無駄ちゃうんや。ほんまに役立つのは、その“知識そのもの”というよりも、“学び方”や“考え方”を身につけることやと思うねん。
たとえば、ワシらが仕事してるとき、上司から「なんでそれを選んだんや?」って聞かれることあるやろ?そのときに、「理由をちゃんと説明できるかどうか」、それはまさに、学校で論理的に考える練習をしとったかどうかで違ってくるんやで。
あと、勉強って、「しんどいな〜」「やりたないな〜」って思う気持ちと付き合う練習にもなる。人生って楽しいことばっかりちゃうやろ?苦手なことも、面倒なことも、逃げられへんときがあるんや。せやけど、学生時代に「イヤやけど、やってみたらできた」って経験があると、ちょっとやそっとのことじゃ折れへん人間になれるんや。
ワシらオッサン世代でも、あのとき勉強してた「なんでこれが大事なんか、わからんけどやる」って姿勢が、今でも生きてるなぁと思う瞬間があるねん。ほんで不思議なことに、若い頃はわからんかったことが、大人になって「なるほど、あれが今につながってるんか!」って腑に落ちる瞬間もあるんや。
せやからな、今すぐ答えが出んくてもええ。せやけど、「これは自分を育ててくれてるんや」って、ちょっとでも感じながら勉強してみたら、案外スッと身につくもんやで。
勉強が将来役に立つかどうかという問いは、教育学において長年議論されてきたテーマだ。結論から述べると、「短期的には役立たないことも多いが、長期的に見れば極めて重要な知的基盤を形成する要素である」と言えるだろう。
まず、数学や古典文学、歴史などの科目は、それ自体が直接的に職業に直結するとは限らない。しかし、それらの学習を通じて人は「抽象的な概念を理解する力」「論理的思考力」「批判的な視点」「情報の取捨選択能力」など、社会人として必要不可欠な“メタ認知的スキル”を獲得しているのである。
さらに、知識は知識を呼ぶ。「知っている」という状態は、単にその分野に詳しいというだけでなく、新しい知識を吸収しやすくし、思考の柔軟性を高める働きもある。これは“スキーマ理論”という心理学的モデルでも示されている。
また、教育心理学の観点からは、「努力する経験」そのものが自己効力感を高めることが示されている。すなわち、「難しかったけど、やりきった」という経験が、自己肯定感を支える柱となるのである。
そして何よりも重要なのは、“学ぶ姿勢”を若い頃に身につけておくことだ。技術革新の速い現代においては、生涯学び続ける力が求められる。学生時代の勉強が、その後の学び直し(リスキリング)の土台となる。
よって、学ぶ内容が「今すぐ使えるか否か」ではなく、「将来の自分の可能性を広げてくれるか」という視点で捉えることが肝要である。
まず、数学や古典文学、歴史などの科目は、それ自体が直接的に職業に直結するとは限らない。しかし、それらの学習を通じて人は「抽象的な概念を理解する力」「論理的思考力」「批判的な視点」「情報の取捨選択能力」など、社会人として必要不可欠な“メタ認知的スキル”を獲得しているのである。
さらに、知識は知識を呼ぶ。「知っている」という状態は、単にその分野に詳しいというだけでなく、新しい知識を吸収しやすくし、思考の柔軟性を高める働きもある。これは“スキーマ理論”という心理学的モデルでも示されている。
また、教育心理学の観点からは、「努力する経験」そのものが自己効力感を高めることが示されている。すなわち、「難しかったけど、やりきった」という経験が、自己肯定感を支える柱となるのである。
そして何よりも重要なのは、“学ぶ姿勢”を若い頃に身につけておくことだ。技術革新の速い現代においては、生涯学び続ける力が求められる。学生時代の勉強が、その後の学び直し(リスキリング)の土台となる。
よって、学ぶ内容が「今すぐ使えるか否か」ではなく、「将来の自分の可能性を広げてくれるか」という視点で捉えることが肝要である。