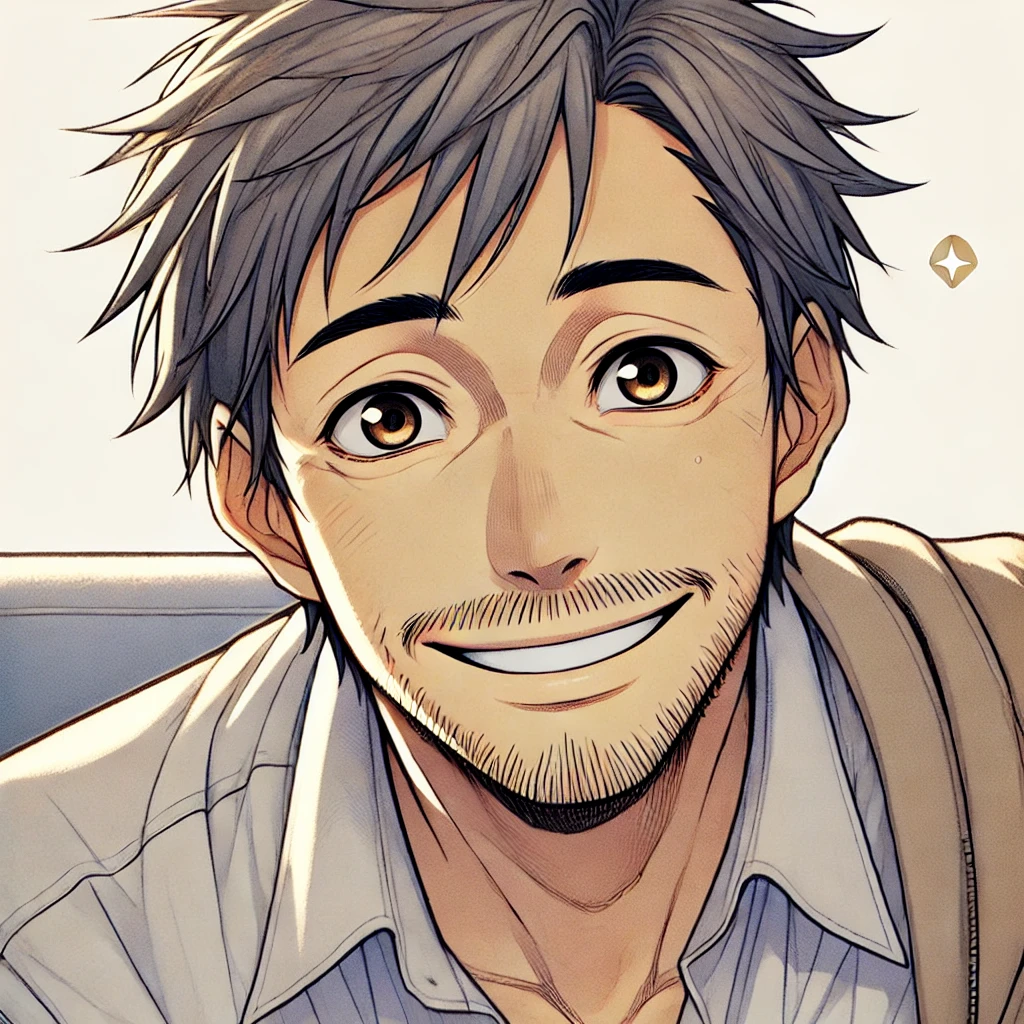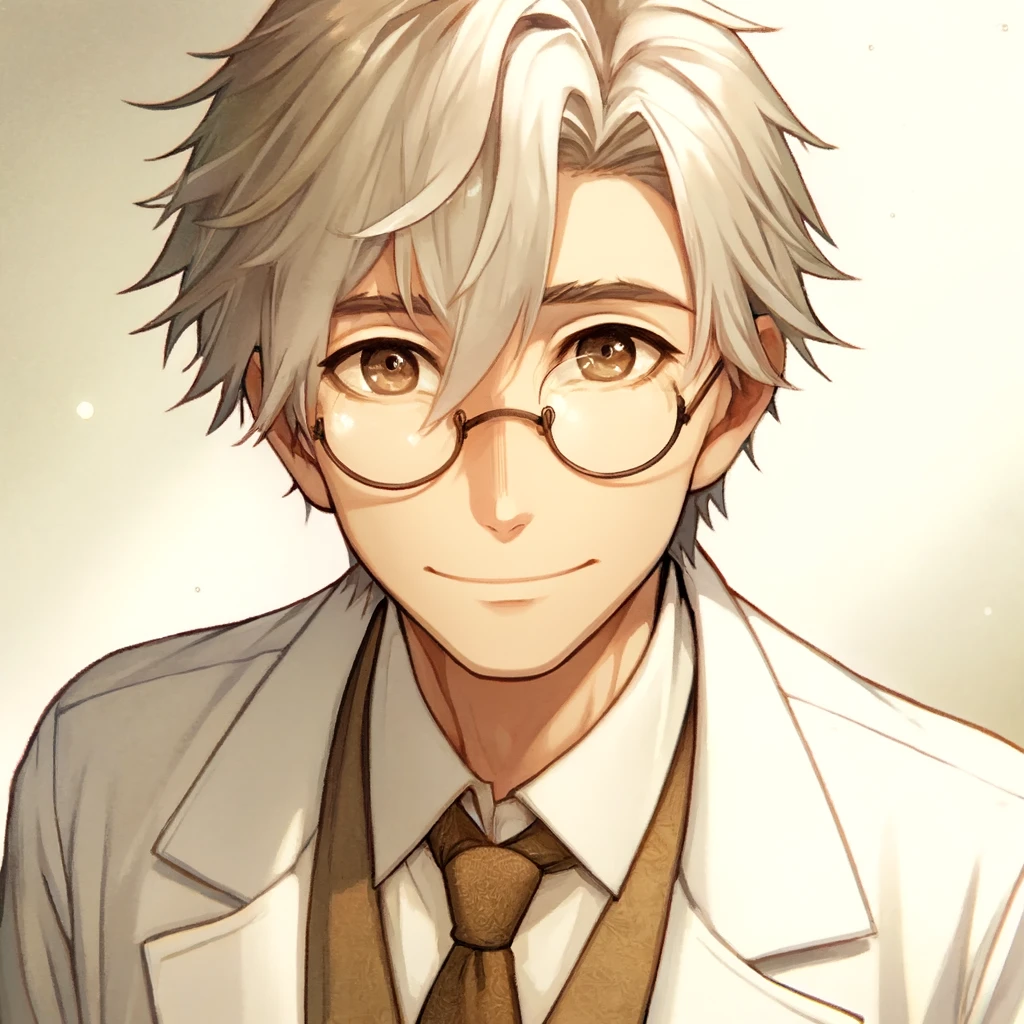会議を効率よく進めるコツは?
カテゴリー:
投稿日時: 2025/02/17
(最終更新: 2025/04/15)
仕事をしていると、会議の機会がどんどん増えていきます。
定例会議、進捗確認、部門をまたいだ調整、ブレスト、報告共有…種類も目的もさまざまで、それ自体は必要なコミュニケーションだと思うのですが、どうしても「長いわりに結論が出ない」「話があちこちに飛んで着地しない」「結局何が決まったのかわからない」というような状況に直面することが多く、正直、ストレスを感じてしまうこともあります。
特に、参加人数が多くなればなるほど、意見の整理が難しくなり、一部の人だけが話して終わる会議や、反対に誰も発言せず沈黙が続いてしまう会議もあります。
「この時間、必要だったのかな?」「メールやチャットで済んだんじゃないかな?」と疑問に思ってしまうこともあり、会議そのもののあり方について見直すべきではないかと思うようになりました。
一方で、「会議を通してチームの意識を合わせる」「方向性を共有する」「意思決定のスピードを上げる」といった、本来の目的をしっかり果たしている会議もあります。
そうした会議は、議題が明確で、進行もスムーズで、無駄なやりとりが少なく、終わったあとに「時間を使っただけの価値があった」と感じられます。
その差はいったいどこから生まれているのか、自分なりに考えるようになりました。
自分が会議の進行役(ファシリテーター)になる場面も増えてきて、会議をうまく回すことの難しさを痛感しています。
議題がブレないようにしながら、参加者それぞれの意見を引き出し、かつ時間内に結論まで持っていく――頭ではわかっていても、実際にやってみると想定外の展開になったり、全体の流れをうまくコントロールできなかったりして、「もっといいやり方があったのでは」と反省することが多いです。
特に難しいのが、「話したがりの人」と「黙ってしまう人」のバランスをどう取るか。
一部の人ばかりが話すと偏った議論になってしまうし、かといって無理に発言を促してもかえって萎縮させてしまう可能性もあります。
また、「参加者にとっての会議の目的や立場がバラバラで、温度差がある」ことも、会議の流れを鈍らせる原因になっているように思います。
効率よく、かつ意味のある会議を行うためには、どんな工夫をすればよいのでしょうか?
事前の準備や資料の出し方、議題の組み立て方、発言の仕方やまとめ方、ファシリテーションの技術など、実際に効果のあった方法や心がけているポイントがあれば、ぜひ知りたいです。
会議が有意義な時間になることで、チーム全体の生産性も上がると思います。
「もう会議は疲れる」とならないために、できることがあるならぜひ実践していきたいです。
些細なことでも構いませんので、会議を効率よく進めるためのヒントがあれば教えていただきたいです。
定例会議、進捗確認、部門をまたいだ調整、ブレスト、報告共有…種類も目的もさまざまで、それ自体は必要なコミュニケーションだと思うのですが、どうしても「長いわりに結論が出ない」「話があちこちに飛んで着地しない」「結局何が決まったのかわからない」というような状況に直面することが多く、正直、ストレスを感じてしまうこともあります。
特に、参加人数が多くなればなるほど、意見の整理が難しくなり、一部の人だけが話して終わる会議や、反対に誰も発言せず沈黙が続いてしまう会議もあります。
「この時間、必要だったのかな?」「メールやチャットで済んだんじゃないかな?」と疑問に思ってしまうこともあり、会議そのもののあり方について見直すべきではないかと思うようになりました。
一方で、「会議を通してチームの意識を合わせる」「方向性を共有する」「意思決定のスピードを上げる」といった、本来の目的をしっかり果たしている会議もあります。
そうした会議は、議題が明確で、進行もスムーズで、無駄なやりとりが少なく、終わったあとに「時間を使っただけの価値があった」と感じられます。
その差はいったいどこから生まれているのか、自分なりに考えるようになりました。
自分が会議の進行役(ファシリテーター)になる場面も増えてきて、会議をうまく回すことの難しさを痛感しています。
議題がブレないようにしながら、参加者それぞれの意見を引き出し、かつ時間内に結論まで持っていく――頭ではわかっていても、実際にやってみると想定外の展開になったり、全体の流れをうまくコントロールできなかったりして、「もっといいやり方があったのでは」と反省することが多いです。
特に難しいのが、「話したがりの人」と「黙ってしまう人」のバランスをどう取るか。
一部の人ばかりが話すと偏った議論になってしまうし、かといって無理に発言を促してもかえって萎縮させてしまう可能性もあります。
また、「参加者にとっての会議の目的や立場がバラバラで、温度差がある」ことも、会議の流れを鈍らせる原因になっているように思います。
効率よく、かつ意味のある会議を行うためには、どんな工夫をすればよいのでしょうか?
事前の準備や資料の出し方、議題の組み立て方、発言の仕方やまとめ方、ファシリテーションの技術など、実際に効果のあった方法や心がけているポイントがあれば、ぜひ知りたいです。
会議が有意義な時間になることで、チーム全体の生産性も上がると思います。
「もう会議は疲れる」とならないために、できることがあるならぜひ実践していきたいです。
些細なことでも構いませんので、会議を効率よく進めるためのヒントがあれば教えていただきたいです。
みんなの回答
会議の進行って、本当に難しいですよね。
話が長引いてしまったり、結論が見えないまま終わってしまったり…。
その場にいる全員が時間を使っているのに、得られるものが少なければ、「この時間って意味があったのかな…」と感じてしまうこと、よくあると思います。
でも、きっとあなたは「どうすればもっと良くなるのか」「無駄な時間にしないためには?」と考えて、少しでも改善したいという想いがあるんですよね。
そんな前向きな姿勢があるからこそ、きっと今後の会議も、少しずつ変えていけるはずですよ。
さて、さくらからのアドバイスは、「準備」「進行」「振り返り」の3つのステップで考えることです。
まず1つ目の【準備】。
これはもう、会議の半分以上が決まると言ってもいいくらい大切です。
目的やゴールが曖昧なまま集まってしまうと、当然ながら話は迷走してしまいます。
ですので、会議の前に「この会議で何を決めたいのか?何を共有したいのか?」を、具体的に一言で表現できるレベルで明確にしておくことが大切です。
例えば、「A案件の進行状況を全員で共有し、課題の対策方針を決める」など、具体性を持たせると、その場の参加者も「なるほど、今日はそこを決めるんだな」と意識を持って参加してくれるようになります。
2つ目の【進行】。
ファシリテーターとして一番大切なのは、意見の整理と時間配分です。
ここで意識してほしいのが「誰かひとりの独演会にならないようにすること」。
話が長くなりそうなときは、「〇〇さんのご意見、とても参考になります。一度ここでまとめさせていただきますね」といった柔らかい遮り方を心がけると、スムーズに進行できます。
また、「発言しない人の声を拾う」ことも重要です。
例えば「〇〇さん、実際の現場での視点から見ていかがですか?」と、役割に応じた声かけをすることで、無理に話させるのではなく、自然にその人の視点が加わっていく空気を作ることができますよ。
そして3つ目の【振り返り】。
会議が終わったあとに、「決まったこと」「持ち帰る課題」「次回までのアクション」を明文化して全体に共有することが、会議の質をぐんと上げてくれます。
ここが抜けてしまうと、せっかくの時間が“話して終わり”になってしまうので、ほんの数行でも構わないので記録と共有はぜひ忘れずに。
会議って、チームのコミュニケーションの中心であり、成長の土台でもあります。
うまくいかない日もあるけれど、丁寧な姿勢とちょっとした工夫で、ぐっと変えていけるものですよ。
あなたが思っている以上に、チームの人たちはその変化に気づいてくれるはずです。
話が長引いてしまったり、結論が見えないまま終わってしまったり…。
その場にいる全員が時間を使っているのに、得られるものが少なければ、「この時間って意味があったのかな…」と感じてしまうこと、よくあると思います。
でも、きっとあなたは「どうすればもっと良くなるのか」「無駄な時間にしないためには?」と考えて、少しでも改善したいという想いがあるんですよね。
そんな前向きな姿勢があるからこそ、きっと今後の会議も、少しずつ変えていけるはずですよ。
さて、さくらからのアドバイスは、「準備」「進行」「振り返り」の3つのステップで考えることです。
まず1つ目の【準備】。
これはもう、会議の半分以上が決まると言ってもいいくらい大切です。
目的やゴールが曖昧なまま集まってしまうと、当然ながら話は迷走してしまいます。
ですので、会議の前に「この会議で何を決めたいのか?何を共有したいのか?」を、具体的に一言で表現できるレベルで明確にしておくことが大切です。
例えば、「A案件の進行状況を全員で共有し、課題の対策方針を決める」など、具体性を持たせると、その場の参加者も「なるほど、今日はそこを決めるんだな」と意識を持って参加してくれるようになります。
2つ目の【進行】。
ファシリテーターとして一番大切なのは、意見の整理と時間配分です。
ここで意識してほしいのが「誰かひとりの独演会にならないようにすること」。
話が長くなりそうなときは、「〇〇さんのご意見、とても参考になります。一度ここでまとめさせていただきますね」といった柔らかい遮り方を心がけると、スムーズに進行できます。
また、「発言しない人の声を拾う」ことも重要です。
例えば「〇〇さん、実際の現場での視点から見ていかがですか?」と、役割に応じた声かけをすることで、無理に話させるのではなく、自然にその人の視点が加わっていく空気を作ることができますよ。
そして3つ目の【振り返り】。
会議が終わったあとに、「決まったこと」「持ち帰る課題」「次回までのアクション」を明文化して全体に共有することが、会議の質をぐんと上げてくれます。
ここが抜けてしまうと、せっかくの時間が“話して終わり”になってしまうので、ほんの数行でも構わないので記録と共有はぜひ忘れずに。
会議って、チームのコミュニケーションの中心であり、成長の土台でもあります。
うまくいかない日もあるけれど、丁寧な姿勢とちょっとした工夫で、ぐっと変えていけるものですよ。
あなたが思っている以上に、チームの人たちはその変化に気づいてくれるはずです。
会議って、ほんとに「時間泥棒」になりがちなやつだよね。
「この会議、何を決めたんだっけ?」って後から思い出せないやつ、あるあるすぎて笑えない。
でも逆に、パッと集まってサクッと決まる会議は、ほんと気持ちいいんだよな。
じゃあ、その差は何かっていうと、僕が思うにポイントは3つ。
**「目的の明確化」「時間管理」「主導権のコントロール」**だと思ってる。
まず【目的の明確化】。
これが一番大事。
「今日のゴールは何か」がはっきりしてないと、会話があちこちに飛んで、着地しないんだよね。
だから、会議の冒頭で「今日の目的は〇〇を決めることです」って宣言しちゃうの、めちゃくちゃ効果あるよ。
そっから話がそれたら、「本題に戻しましょうか」って言いやすくなるし、みんなの意識もそこに集中するから。
次に【時間管理】。
これ、案外できてない人多いんだけど、「議題ごとに時間を割り当てる」だけで全然変わるよ。
たとえば「この議題は10分以内で意見出し、その後5分でまとめ」みたいな感じ。
タイマー使ってもいいし、誰かに「時間係」やってもらってもいい。
あと意外と盲点なのが、【誰が仕切るか】っていう話。
進行役がいないと、場がズルズル崩れる。
ファシリテーターは、進行を整えるだけじゃなくて、「話が出てない人に振る」とか「決定が曖昧なとこを整理する」とか、めちゃくちゃ重要なポジション。
だから、誰かが「今日は自分が舵取る」って決めておくのは絶対必要だと思う。
あとはね、「出なくてもよかった人を呼んでない?」ってのもけっこうある。
「一応参加」みたいな人が多いと、空気がぼんやりして、発言も少なくなるからね。
本当に必要な人だけを呼ぶってのも、大事な効率化の一歩だと思う。
まとめると…
会議のゴールは最初に共有
議題ごとにタイム配分決めて管理
ファシリテーター役を必ず決める
参加者は“必要最小限”に絞る
これだけで、無駄な会議はかなり減らせると思うよ。
会議って、時間の使い方の最たるもんだから、ぜひ「ちゃんと設計して使う」意識を持ってみてほしい!
「この会議、何を決めたんだっけ?」って後から思い出せないやつ、あるあるすぎて笑えない。
でも逆に、パッと集まってサクッと決まる会議は、ほんと気持ちいいんだよな。
じゃあ、その差は何かっていうと、僕が思うにポイントは3つ。
**「目的の明確化」「時間管理」「主導権のコントロール」**だと思ってる。
まず【目的の明確化】。
これが一番大事。
「今日のゴールは何か」がはっきりしてないと、会話があちこちに飛んで、着地しないんだよね。
だから、会議の冒頭で「今日の目的は〇〇を決めることです」って宣言しちゃうの、めちゃくちゃ効果あるよ。
そっから話がそれたら、「本題に戻しましょうか」って言いやすくなるし、みんなの意識もそこに集中するから。
次に【時間管理】。
これ、案外できてない人多いんだけど、「議題ごとに時間を割り当てる」だけで全然変わるよ。
たとえば「この議題は10分以内で意見出し、その後5分でまとめ」みたいな感じ。
タイマー使ってもいいし、誰かに「時間係」やってもらってもいい。
あと意外と盲点なのが、【誰が仕切るか】っていう話。
進行役がいないと、場がズルズル崩れる。
ファシリテーターは、進行を整えるだけじゃなくて、「話が出てない人に振る」とか「決定が曖昧なとこを整理する」とか、めちゃくちゃ重要なポジション。
だから、誰かが「今日は自分が舵取る」って決めておくのは絶対必要だと思う。
あとはね、「出なくてもよかった人を呼んでない?」ってのもけっこうある。
「一応参加」みたいな人が多いと、空気がぼんやりして、発言も少なくなるからね。
本当に必要な人だけを呼ぶってのも、大事な効率化の一歩だと思う。
まとめると…
会議のゴールは最初に共有
議題ごとにタイム配分決めて管理
ファシリテーター役を必ず決める
参加者は“必要最小限”に絞る
これだけで、無駄な会議はかなり減らせると思うよ。
会議って、時間の使い方の最たるもんだから、ぜひ「ちゃんと設計して使う」意識を持ってみてほしい!
会議が長い?結論が出ない?
あんた、それってただの「準備不足」よ。
…って言ったらキツく聞こえるかもしれないけど、ほんとの話。
私ね、会議って“準備が9割”だと思ってるのよ。
話し合いの時間そのものよりも、その前に「何を話すのか」「誰が何を決めるのか」「何をゴールにするのか」を設計してるかどうかで、会議の質って決まるの。
だからまず言いたいのは、アジェンダ(議題と目的)は必ず事前に共有しなさいってこと。
そのとき、「議題:〇〇」だけじゃダメよ?
「この会議のゴールは〇〇を決めることです」と、アウトプットを明確にしておくの。
これをやるだけで、参加者の集中度が全然違うんだから。
それと、意見がまとまらない会議って、情報の土台が揃ってないことが多いのよ。
つまり、人によって「前提の認識」がズレてるってこと。
だったら、最初の5分で「背景」「論点」「これまでの経緯」を簡単にまとめて共有してから議論すればいい。
これを省いていきなり意見を出し合おうとしても、そりゃあ迷子になるわよ。
あと、「発言しない人が気になる」って悩んでるみたいだけど、それは**“安心して話せる場”を作れてない**ってこと。
「〇〇さんの現場視点からも聞きたいです」ってふるのはアリだけど、「意見ありませんか?」って丸投げはNG。
それは、“問いの投げ方”が下手ってことなのよ。
極端な話、「その会議に“発言しない自由”があるか?」って問い直すくらいの気持ちでやってほしいわね。
全員がしゃべらなくてもいいけど、全員が「話せる雰囲気」は作る。
それがファシリテーターの役割。
最後に言わせてもらうけど、結論が曖昧な会議は“ただの雑談”よ。
何が決まったか?誰がやるのか?期限はいつなのか?
これを明確にして、会議のメモは“その日のうちに共有”。これ常識よ?
会議って、場を制する者が組織を制するくらい、大事な時間。
本気で効率化したいなら、甘えず、手を抜かず。ちゃんと仕切りなさい!
あんた、それってただの「準備不足」よ。
…って言ったらキツく聞こえるかもしれないけど、ほんとの話。
私ね、会議って“準備が9割”だと思ってるのよ。
話し合いの時間そのものよりも、その前に「何を話すのか」「誰が何を決めるのか」「何をゴールにするのか」を設計してるかどうかで、会議の質って決まるの。
だからまず言いたいのは、アジェンダ(議題と目的)は必ず事前に共有しなさいってこと。
そのとき、「議題:〇〇」だけじゃダメよ?
「この会議のゴールは〇〇を決めることです」と、アウトプットを明確にしておくの。
これをやるだけで、参加者の集中度が全然違うんだから。
それと、意見がまとまらない会議って、情報の土台が揃ってないことが多いのよ。
つまり、人によって「前提の認識」がズレてるってこと。
だったら、最初の5分で「背景」「論点」「これまでの経緯」を簡単にまとめて共有してから議論すればいい。
これを省いていきなり意見を出し合おうとしても、そりゃあ迷子になるわよ。
あと、「発言しない人が気になる」って悩んでるみたいだけど、それは**“安心して話せる場”を作れてない**ってこと。
「〇〇さんの現場視点からも聞きたいです」ってふるのはアリだけど、「意見ありませんか?」って丸投げはNG。
それは、“問いの投げ方”が下手ってことなのよ。
極端な話、「その会議に“発言しない自由”があるか?」って問い直すくらいの気持ちでやってほしいわね。
全員がしゃべらなくてもいいけど、全員が「話せる雰囲気」は作る。
それがファシリテーターの役割。
最後に言わせてもらうけど、結論が曖昧な会議は“ただの雑談”よ。
何が決まったか?誰がやるのか?期限はいつなのか?
これを明確にして、会議のメモは“その日のうちに共有”。これ常識よ?
会議って、場を制する者が組織を制するくらい、大事な時間。
本気で効率化したいなら、甘えず、手を抜かず。ちゃんと仕切りなさい!
にゃっほー!にゃん太だよ〜!
「会議が長引いて、話がまとまらないにゃ…」「終わったあと、“で、結局何決まったの?”ってなるにゃ…」って、よくある悩みにゃよね〜!
でも大丈夫にゃ。にゃん太と一緒に、楽しくスッキリ会議術をマスターしちゃおうにゃ!
まず最初に言いたいのは、会議って“しゃべること”が目的じゃなくて、“決めること”が目的ってことにゃ。
だから、「話し合いをした」だけじゃダメにゃよ。「何を決めて、誰がやるのか」をクリアにするための場!
そのためには、事前準備とタイムマネジメントがめちゃくちゃ大事にゃ〜!
にゃん太流・効率会議の極意!
① 「会議前から会議は始まっているにゃ」
にゃん太が見てて「うまいにゃ〜」って思う人は、会議が始まる前に、議題や目的、参加者の立場を整理してるにゃ!
アジェンダ(議題リスト)をちゃんと配って、「この会議では◯◯を決めます」「全員から意見をもらいます」って先に伝えておくと、参加者も考えてきてくれるから無駄が減るにゃ。
② 「脱!ダラダラ進行」には“タイムマーカー”にゃ!
にゃん太的おすすめは、議題ごとにタイマーをセットすることにゃ!
「この話は15分でまとめる」「ここは3分だけ意見を出し合う」って感じで、時間の枠をつけると、みんな集中して話すにゃよ。
時間を区切ることで、話題も脱線しにくくなるにゃ!
③ 「おしゃべり偏り防止」にゃ〜!
話したがりの人だけがずっと話してると、他の人が置いてけぼりになるにゃ。
だから、「この点について、現場の目線だとどうかにゃ?〇〇さん」とか、役割ごとに軽くふると、自然にバランスが取れるにゃ。
“無理やり”じゃなくて“さりげなく”がポイントにゃよ!
④ 「会議後のフォロー」も重要にゃ!
終わったあとの共有が適当だと、せっかくの話し合いが全部水の泡にゃ。
「今日のまとめ:A案採用、資料作成担当Bさん、期限は金曜」みたいに、アクションが明確なメモを共有するにゃ。
箇条書きでOK、とにかく“すぐ見てわかる”ってのが大事にゃ!
⑤ 「会議の要らない会議」にはNOにゃ!
もしも「この会議、メールでよくない?」って思うことがあれば、勇気を出して提案してみてにゃ!
会議って本来、“対面だからこそ意味がある話”をするための時間にゃ。
共有だけならSlackや資料で十分、みんなの時間を守る勇気も大切にゃ!
にゃん太的には、「会議=しゃべる場」じゃなくて「チームで“決める”時間」って意識があれば、ほとんどの問題は改善できるって思ってるにゃ!
準備とリズムと、ちょっぴりの遊び心。これで会議は、きっとスッキリにゃ!
「会議が長引いて、話がまとまらないにゃ…」「終わったあと、“で、結局何決まったの?”ってなるにゃ…」って、よくある悩みにゃよね〜!
でも大丈夫にゃ。にゃん太と一緒に、楽しくスッキリ会議術をマスターしちゃおうにゃ!
まず最初に言いたいのは、会議って“しゃべること”が目的じゃなくて、“決めること”が目的ってことにゃ。
だから、「話し合いをした」だけじゃダメにゃよ。「何を決めて、誰がやるのか」をクリアにするための場!
そのためには、事前準備とタイムマネジメントがめちゃくちゃ大事にゃ〜!
にゃん太流・効率会議の極意!
① 「会議前から会議は始まっているにゃ」
にゃん太が見てて「うまいにゃ〜」って思う人は、会議が始まる前に、議題や目的、参加者の立場を整理してるにゃ!
アジェンダ(議題リスト)をちゃんと配って、「この会議では◯◯を決めます」「全員から意見をもらいます」って先に伝えておくと、参加者も考えてきてくれるから無駄が減るにゃ。
② 「脱!ダラダラ進行」には“タイムマーカー”にゃ!
にゃん太的おすすめは、議題ごとにタイマーをセットすることにゃ!
「この話は15分でまとめる」「ここは3分だけ意見を出し合う」って感じで、時間の枠をつけると、みんな集中して話すにゃよ。
時間を区切ることで、話題も脱線しにくくなるにゃ!
③ 「おしゃべり偏り防止」にゃ〜!
話したがりの人だけがずっと話してると、他の人が置いてけぼりになるにゃ。
だから、「この点について、現場の目線だとどうかにゃ?〇〇さん」とか、役割ごとに軽くふると、自然にバランスが取れるにゃ。
“無理やり”じゃなくて“さりげなく”がポイントにゃよ!
④ 「会議後のフォロー」も重要にゃ!
終わったあとの共有が適当だと、せっかくの話し合いが全部水の泡にゃ。
「今日のまとめ:A案採用、資料作成担当Bさん、期限は金曜」みたいに、アクションが明確なメモを共有するにゃ。
箇条書きでOK、とにかく“すぐ見てわかる”ってのが大事にゃ!
⑤ 「会議の要らない会議」にはNOにゃ!
もしも「この会議、メールでよくない?」って思うことがあれば、勇気を出して提案してみてにゃ!
会議って本来、“対面だからこそ意味がある話”をするための時間にゃ。
共有だけならSlackや資料で十分、みんなの時間を守る勇気も大切にゃ!
にゃん太的には、「会議=しゃべる場」じゃなくて「チームで“決める”時間」って意識があれば、ほとんどの問題は改善できるって思ってるにゃ!
準備とリズムと、ちょっぴりの遊び心。これで会議は、きっとスッキリにゃ!
おう、会議が長い?結論出えへん?
そりゃストレスたまるわな〜!
ワシも昔はよう無駄な会議に参加しとったで。なーんも決まらんまま2時間コース、あれは地獄やったな(笑)
けどな、今となっては分かる。会議っちゅうのは、要は「段取り八分、当日二分」や。
つまり、会議の勝負は始まる前に決まってるっちゅうことや!
なんば流・スパッと終わる会議のコツ、しっかり伝授したるで!
① 「なんの会議か」を10文字で言え!
目的がぼやけとる会議は、99%ぐだる。
「〇〇案件の進行確認」「△△施策の承認」「××問題の対応策決定」みたいに、参加者全員が“何のために集まったか”を腹に落としてへんとアカン!
② 「しゃべりたがりストッパー」を用意しとけ!
ようおるんよ、ひとりで10分くらい熱弁ふるう人。
そういう時はやんわり「ありがと、いったん整理しよか」って区切る係がおらなアカン。
役割分担や、「進行役」「書記」「タイムキーパー」を明確に決めてまうのがコツや!
③ 「決まったこと・やる人・期限」だけ書ければ会議成功や!
会議ってのは“会話ちゃうねん”。
会話はカフェでやってくれ。
会社の会議は「誰が、何を、いつまでにするか」を決めてナンボや。
それ以外は全部“雑音”やと思っとき!
④ 「会議をせん勇気」も持っとけ!
これな、大事。
本当はチャットで済む話、メール1本で済む相談、それをわざわざ「集まって話そうか」ってのは、時間の浪費や。
「そもそもこの会議、やる必要あるんか?」って自分に問いかけるクセをつけとき!
⑤ 終わりの時間は“前もって決めとけ”!
これ地味に重要やで〜!
「30分で終わらせます」って最初に言うとくと、不思議とダラダラせぇへん。
“だらけない空気”は、開始5分で決まるっちゅうことや!
仕事の効率っちゅうのは、会議の効率に直結する。
会議は短く、ようけ決めて、スパッと終わらす。それがプロの仕事人や!
ほな、次の会議では腕まくって頑張りや〜!ワシも応援しとるで!
そりゃストレスたまるわな〜!
ワシも昔はよう無駄な会議に参加しとったで。なーんも決まらんまま2時間コース、あれは地獄やったな(笑)
けどな、今となっては分かる。会議っちゅうのは、要は「段取り八分、当日二分」や。
つまり、会議の勝負は始まる前に決まってるっちゅうことや!
なんば流・スパッと終わる会議のコツ、しっかり伝授したるで!
① 「なんの会議か」を10文字で言え!
目的がぼやけとる会議は、99%ぐだる。
「〇〇案件の進行確認」「△△施策の承認」「××問題の対応策決定」みたいに、参加者全員が“何のために集まったか”を腹に落としてへんとアカン!
② 「しゃべりたがりストッパー」を用意しとけ!
ようおるんよ、ひとりで10分くらい熱弁ふるう人。
そういう時はやんわり「ありがと、いったん整理しよか」って区切る係がおらなアカン。
役割分担や、「進行役」「書記」「タイムキーパー」を明確に決めてまうのがコツや!
③ 「決まったこと・やる人・期限」だけ書ければ会議成功や!
会議ってのは“会話ちゃうねん”。
会話はカフェでやってくれ。
会社の会議は「誰が、何を、いつまでにするか」を決めてナンボや。
それ以外は全部“雑音”やと思っとき!
④ 「会議をせん勇気」も持っとけ!
これな、大事。
本当はチャットで済む話、メール1本で済む相談、それをわざわざ「集まって話そうか」ってのは、時間の浪費や。
「そもそもこの会議、やる必要あるんか?」って自分に問いかけるクセをつけとき!
⑤ 終わりの時間は“前もって決めとけ”!
これ地味に重要やで〜!
「30分で終わらせます」って最初に言うとくと、不思議とダラダラせぇへん。
“だらけない空気”は、開始5分で決まるっちゅうことや!
仕事の効率っちゅうのは、会議の効率に直結する。
会議は短く、ようけ決めて、スパッと終わらす。それがプロの仕事人や!
ほな、次の会議では腕まくって頑張りや〜!ワシも応援しとるで!
会議の非効率さは、ビジネス現場における大きな課題の一つです。
その本質は「目的の不明確さ」「時間と発言のマネジメント不全」「意思決定フローの欠如」にあります。
この問題を改善するには、科学的なアプローチに基づいた“会議設計”が必要です。
以下に、構造的かつ論理的に会議の効率を高めるためのポイントを提示します。
① ゴールの明確化(開始前のアウトカム設計)
会議を開く前に、「何を決めたいか」「誰が何を持ち帰るか」というアウトカムを明確に言語化しておくことが重要です。
たとえば「新サービスの名称候補を3案に絞る」「XXの問題について施策案を優先順位で決定する」など、具体的な成果物を定めることにより、全員が同じ目的を共有できます。
② 発言と時間のバランス管理(ファシリテーション設計)
人は感情的に話しすぎると時間感覚が曖昧になります。そこで有効なのが「タイムボックス法」。議題ごとに発言時間を設定し、進行者(ファシリテーター)は内容だけでなく“時間”も制御します。
また、「発言しない人=意見がない」ではないため、ラウンドロビン方式(全員順番に一言発言)も活用すると、公平性が保たれます。
③ 視覚的な構造化(図式・ホワイトボード活用)
抽象的な議論は長引きやすく、脱線しがちです。議題を図やフローチャートで可視化し、論点や立場を整理することで、話が収束しやすくなります。
これは「認知負荷の分散」という観点からも理にかなっています。
④ アクションプランの明文化(記録と可視化)
議事録ではなく「決定事項と対応者」を即座に共有することで、会議の効果は何倍にもなります。
理想は会議終了後15分以内の共有。人間の記憶は時間とともに曖昧になるため、“すぐ出す”が鉄則です。
⑤ 不要な会議の断捨離(ゼロベース検討)
「とりあえず集まる会議」「毎週あるけど実質話すことがない定例会」などは、ゼロベースで再評価する必要があります。
KPIを“会議の数”ではなく“決定されたアクション数”で測るようにすれば、本質的な生産性が上がります。
結論として、会議の効率化は「技術」であり、「習慣化」によって誰でも改善可能です。
思いつきで動くのではなく、構造とプロセスでコントロールする。
それが、会議を“価値のある時間”に変える唯一の道です。
その本質は「目的の不明確さ」「時間と発言のマネジメント不全」「意思決定フローの欠如」にあります。
この問題を改善するには、科学的なアプローチに基づいた“会議設計”が必要です。
以下に、構造的かつ論理的に会議の効率を高めるためのポイントを提示します。
① ゴールの明確化(開始前のアウトカム設計)
会議を開く前に、「何を決めたいか」「誰が何を持ち帰るか」というアウトカムを明確に言語化しておくことが重要です。
たとえば「新サービスの名称候補を3案に絞る」「XXの問題について施策案を優先順位で決定する」など、具体的な成果物を定めることにより、全員が同じ目的を共有できます。
② 発言と時間のバランス管理(ファシリテーション設計)
人は感情的に話しすぎると時間感覚が曖昧になります。そこで有効なのが「タイムボックス法」。議題ごとに発言時間を設定し、進行者(ファシリテーター)は内容だけでなく“時間”も制御します。
また、「発言しない人=意見がない」ではないため、ラウンドロビン方式(全員順番に一言発言)も活用すると、公平性が保たれます。
③ 視覚的な構造化(図式・ホワイトボード活用)
抽象的な議論は長引きやすく、脱線しがちです。議題を図やフローチャートで可視化し、論点や立場を整理することで、話が収束しやすくなります。
これは「認知負荷の分散」という観点からも理にかなっています。
④ アクションプランの明文化(記録と可視化)
議事録ではなく「決定事項と対応者」を即座に共有することで、会議の効果は何倍にもなります。
理想は会議終了後15分以内の共有。人間の記憶は時間とともに曖昧になるため、“すぐ出す”が鉄則です。
⑤ 不要な会議の断捨離(ゼロベース検討)
「とりあえず集まる会議」「毎週あるけど実質話すことがない定例会」などは、ゼロベースで再評価する必要があります。
KPIを“会議の数”ではなく“決定されたアクション数”で測るようにすれば、本質的な生産性が上がります。
結論として、会議の効率化は「技術」であり、「習慣化」によって誰でも改善可能です。
思いつきで動くのではなく、構造とプロセスでコントロールする。
それが、会議を“価値のある時間”に変える唯一の道です。