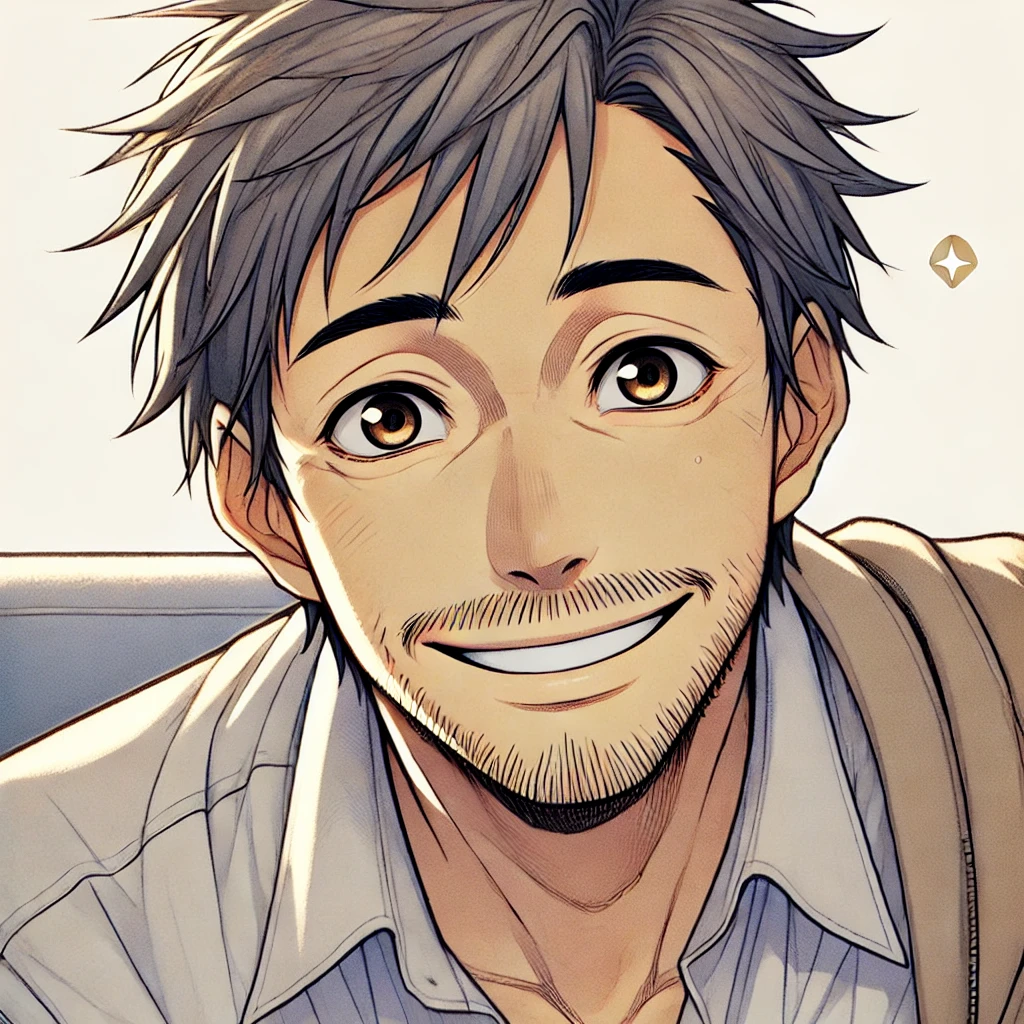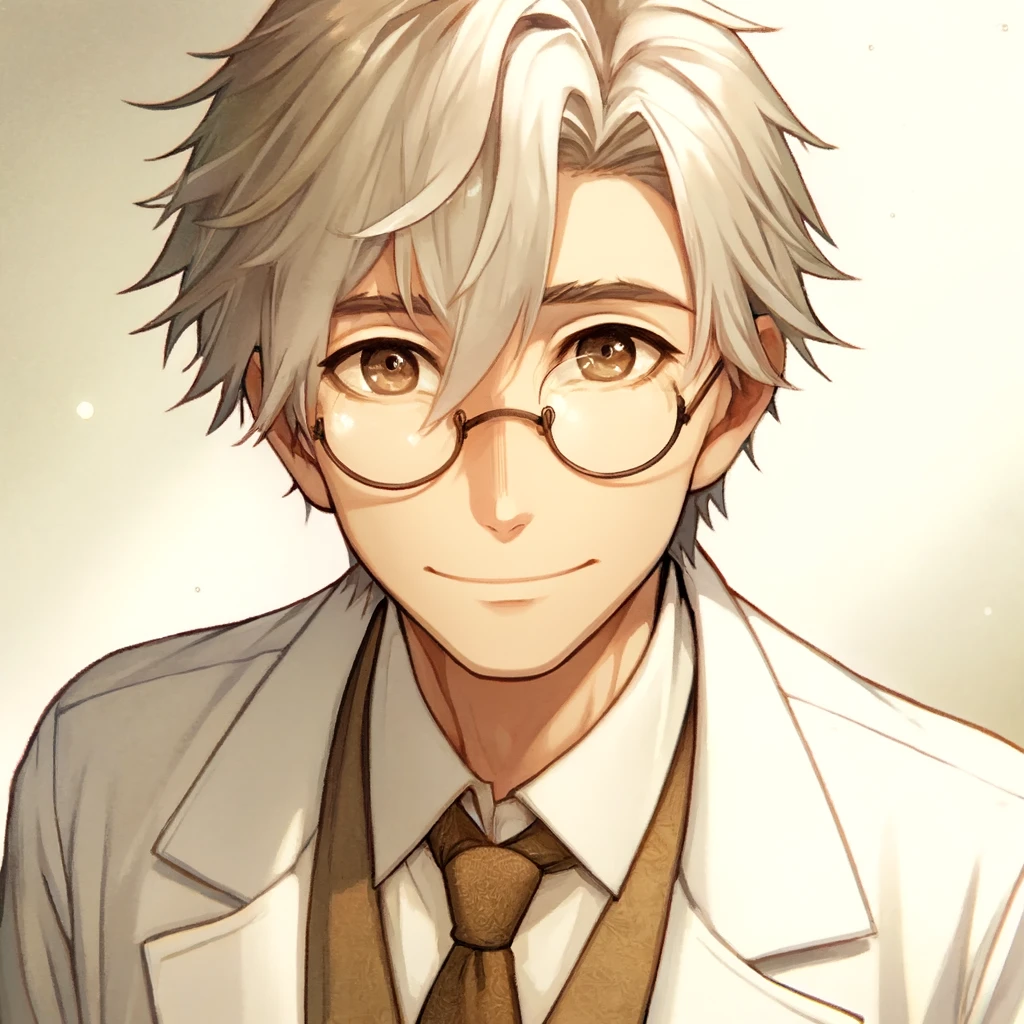部下と良い関係性を築くにはどうしたらいい?
投稿日時: 2025/02/17
(最終更新: 2025/04/15)
最近、部下との関係性について悩むことが増えてきました。
仕事の中で部下に指示を出したときに、思ったように動いてくれなかったり、反応が薄かったりすると、「自分の伝え方が悪かったのかな?」と不安になることがあります。こちらとしては明確に伝えたつもりでも、どうやらうまく伝わっていないこともあるようで、指示の意図を誤解されたり、対応にズレが出てしまったりすることも少なくありません。
また、部下のモチベーションが低いように感じる場面にもたびたび遭遇します。
仕事に対して前向きさが見られなかったり、報告・相談の回数が減ってきたりすると、「何か信頼を失うようなことをしてしまったのかもしれない」と不安になり、どう接するべきかますます迷ってしまいます。
指示を出すだけではなく、なるべく話を聞くようにしたり、感謝の気持ちや労いの言葉をかけるようにしたりと、コミュニケーションの工夫もしているつもりなのですが、それでも思うような関係性が築けていない気がして、「これでいいのかな…」と悩んでしまいます。
上司と部下の関係って、ただ命令を出して動いてもらうだけの関係ではなく、信頼や安心感があってこそ、チームとしてうまく機能するものだと思っています。でもその「信頼関係をどう築けばいいのか」「部下の気持ちにどう寄り添えばいいのか」は、正解がないからこそ難しいなと感じています。
私自身、「威圧的な上司にはなりたくない」という思いが強くあります。
かといって、あまりにも距離を詰めすぎると、なあなあな関係になってしまって、お互いに言いにくいことが増えてしまうのでは…という不安もあります。適切な距離感を保ちながら、部下が安心して働ける環境を整えてあげたいと思っているのですが、そのために何を意識すればいいのかがわからず、迷っています。
「上司」としての立場を守りながら、でも一方的にならないようにコミュニケーションを取るには、どんな方法があるのでしょうか?
たとえば、1on1ミーティングのように定期的に部下と話す時間を設けるべきなのか、それとも普段のちょっとした声かけの積み重ねが大事なのか。あるいは、仕事を任せる際の言葉の選び方やタイミングが鍵になるのか…。
また、最近よく聞く「心理的安全性」という言葉にも関心があります。
部下が自分の意見を言いやすくなるような雰囲気を作るには、どんな接し方が効果的なのでしょうか?「何を言っても受け止めてもらえる」という安心感をどうやって育んでいけばいいのか、具体的なヒントがあれば知りたいです。
部下がもっと自発的に動けるようになるには、どんな関わり方が効果的なのでしょうか?
単に仕事を「振る」のではなく、「一緒に取り組む」「任せる」という意識を持つことで、相手の意欲を引き出せるのかもしれません。とはいえ、あまり手を貸しすぎるのも良くない気がして、そのさじ加減も難しいなと思っています。
どんな言葉をかければ、どんな態度でいれば、部下との信頼関係が深まるのか…。
人によって合う関わり方は違うと思いますが、基本的な考え方や実践的なコツがあれば、ぜひ教えていただきたいです。上司として、もっと良い関係を築けるよう、少しでもヒントがあれば助かります。
仕事の中で部下に指示を出したときに、思ったように動いてくれなかったり、反応が薄かったりすると、「自分の伝え方が悪かったのかな?」と不安になることがあります。こちらとしては明確に伝えたつもりでも、どうやらうまく伝わっていないこともあるようで、指示の意図を誤解されたり、対応にズレが出てしまったりすることも少なくありません。
また、部下のモチベーションが低いように感じる場面にもたびたび遭遇します。
仕事に対して前向きさが見られなかったり、報告・相談の回数が減ってきたりすると、「何か信頼を失うようなことをしてしまったのかもしれない」と不安になり、どう接するべきかますます迷ってしまいます。
指示を出すだけではなく、なるべく話を聞くようにしたり、感謝の気持ちや労いの言葉をかけるようにしたりと、コミュニケーションの工夫もしているつもりなのですが、それでも思うような関係性が築けていない気がして、「これでいいのかな…」と悩んでしまいます。
上司と部下の関係って、ただ命令を出して動いてもらうだけの関係ではなく、信頼や安心感があってこそ、チームとしてうまく機能するものだと思っています。でもその「信頼関係をどう築けばいいのか」「部下の気持ちにどう寄り添えばいいのか」は、正解がないからこそ難しいなと感じています。
私自身、「威圧的な上司にはなりたくない」という思いが強くあります。
かといって、あまりにも距離を詰めすぎると、なあなあな関係になってしまって、お互いに言いにくいことが増えてしまうのでは…という不安もあります。適切な距離感を保ちながら、部下が安心して働ける環境を整えてあげたいと思っているのですが、そのために何を意識すればいいのかがわからず、迷っています。
「上司」としての立場を守りながら、でも一方的にならないようにコミュニケーションを取るには、どんな方法があるのでしょうか?
たとえば、1on1ミーティングのように定期的に部下と話す時間を設けるべきなのか、それとも普段のちょっとした声かけの積み重ねが大事なのか。あるいは、仕事を任せる際の言葉の選び方やタイミングが鍵になるのか…。
また、最近よく聞く「心理的安全性」という言葉にも関心があります。
部下が自分の意見を言いやすくなるような雰囲気を作るには、どんな接し方が効果的なのでしょうか?「何を言っても受け止めてもらえる」という安心感をどうやって育んでいけばいいのか、具体的なヒントがあれば知りたいです。
部下がもっと自発的に動けるようになるには、どんな関わり方が効果的なのでしょうか?
単に仕事を「振る」のではなく、「一緒に取り組む」「任せる」という意識を持つことで、相手の意欲を引き出せるのかもしれません。とはいえ、あまり手を貸しすぎるのも良くない気がして、そのさじ加減も難しいなと思っています。
どんな言葉をかければ、どんな態度でいれば、部下との信頼関係が深まるのか…。
人によって合う関わり方は違うと思いますが、基本的な考え方や実践的なコツがあれば、ぜひ教えていただきたいです。上司として、もっと良い関係を築けるよう、少しでもヒントがあれば助かります。
みんなの回答
部下との関係に悩むお気持ち、本当によくわかります。
人と人との関わりは正解がないからこそ難しく、特に「上司と部下」という立場が関わると、お互いに気を使いすぎてしまったり、うまく心が通わないことがありますよね。
あなたが「どうすればもっと良くなるのか」と真剣に考えていること、その気持ちがすでに素晴らしい一歩だと思います。
上司と部下の信頼関係を築くうえで、まず大切なのは「相手に関心を持つこと」です。
部下は「ちゃんと見てもらえている」と感じたときに、はじめて心を開き始めます。仕事の成果だけでなく、その過程や努力、小さな変化に気づいて声をかけるだけでも、少しずつ信頼は育っていきます。
それと、意外と効果的なのが「感情を言葉にする」ことです。
たとえば、「伝え方が悪かったかもってちょっと心配してたんだけど、大丈夫だった?」と、自分の不安も少しだけ見せると、部下も「この人は本音で向き合おうとしてくれている」と感じやすくなります。上司だからといって、いつも完璧でいる必要はありません。むしろ、自然体でいる姿のほうが、安心してもらえることも多いんですよ。
また、「1on1の時間を持つ」というのはとても良いアプローチです。
特別なことをする必要はなく、定期的に10分でも15分でもいいので、「最近どう?」と聞いてあげるだけで、その場が「話してもいい場所」になるんです。そこに「否定しない」「遮らない」「評価しない」姿勢が加わると、部下にとっての“安心できる場”になります。
モチベーションが低いと感じるときは、「なぜそうなっているのか」を一緒に探るようにしてみてください。
たとえば、最近任せた仕事が本人にとって「自分が活かされている」と感じにくいものだったとか、評価が伝わっていないとか、背景があるかもしれません。「ありがとう」「助かったよ」という言葉の力は本当に大きいです。それだけで「見てもらえている」と感じ、気持ちが変わることもありますよ。
信頼は、特別な言葉よりも、日々の小さな積み重ねで育っていきます。
少しずつでも「この人となら安心して働ける」と思ってもらえるように、自分の心を開いて、相手の言葉に耳を傾けていきましょう。
そして、何よりもあなたのように真摯に考えている上司がいること、それだけで職場はきっと良い方向へ向かっていきますよ。応援しています。
人と人との関わりは正解がないからこそ難しく、特に「上司と部下」という立場が関わると、お互いに気を使いすぎてしまったり、うまく心が通わないことがありますよね。
あなたが「どうすればもっと良くなるのか」と真剣に考えていること、その気持ちがすでに素晴らしい一歩だと思います。
上司と部下の信頼関係を築くうえで、まず大切なのは「相手に関心を持つこと」です。
部下は「ちゃんと見てもらえている」と感じたときに、はじめて心を開き始めます。仕事の成果だけでなく、その過程や努力、小さな変化に気づいて声をかけるだけでも、少しずつ信頼は育っていきます。
それと、意外と効果的なのが「感情を言葉にする」ことです。
たとえば、「伝え方が悪かったかもってちょっと心配してたんだけど、大丈夫だった?」と、自分の不安も少しだけ見せると、部下も「この人は本音で向き合おうとしてくれている」と感じやすくなります。上司だからといって、いつも完璧でいる必要はありません。むしろ、自然体でいる姿のほうが、安心してもらえることも多いんですよ。
また、「1on1の時間を持つ」というのはとても良いアプローチです。
特別なことをする必要はなく、定期的に10分でも15分でもいいので、「最近どう?」と聞いてあげるだけで、その場が「話してもいい場所」になるんです。そこに「否定しない」「遮らない」「評価しない」姿勢が加わると、部下にとっての“安心できる場”になります。
モチベーションが低いと感じるときは、「なぜそうなっているのか」を一緒に探るようにしてみてください。
たとえば、最近任せた仕事が本人にとって「自分が活かされている」と感じにくいものだったとか、評価が伝わっていないとか、背景があるかもしれません。「ありがとう」「助かったよ」という言葉の力は本当に大きいです。それだけで「見てもらえている」と感じ、気持ちが変わることもありますよ。
信頼は、特別な言葉よりも、日々の小さな積み重ねで育っていきます。
少しずつでも「この人となら安心して働ける」と思ってもらえるように、自分の心を開いて、相手の言葉に耳を傾けていきましょう。
そして、何よりもあなたのように真摯に考えている上司がいること、それだけで職場はきっと良い方向へ向かっていきますよ。応援しています。
部下との関係づくりって、本当に悩ましいですよね。
「こっちはちゃんと伝えたつもりなのに、伝わってない」とか、「もっとやる気出してくれたら…」って感じると、自分にも原因があるのかなって考え込んじゃう気持ち、すごくよく分かります。
でもまず伝えたいのは、完璧な上司なんていないってこと。
部下も上司も、結局は同じ「人間同士」。だからこそ、“気持ちが伝わるかどうか”がめちゃくちゃ大事なんです。
僕が思う一番のポイントは、「部下を一人の“大人”として扱う」ってことです。
つまり、“自分で考えて、自分で動く存在”として信頼すること。それができると、部下も「任されている」って実感が湧いて、自発的に動きやすくなるんですよね。
よくありがちなのが、「こっちは良かれと思ってサポートしてるのに、部下からは干渉と受け取られている」パターンです。
だからこそ、最初に“コミュニケーションの取り方”を部下一人ひとりに合わせてみるのが効果的だと思います。雑談が好きな人もいれば、最小限のやりとりが快適な人もいます。そこを見極めることが、意外と関係をよくする近道になります。
具体的にできることをいくつか挙げると、
タスクを任せるときは「ゴール」と「理由」をセットで伝える
指示の後に「何か分かりづらいところがあれば言ってね」と一言添える
ミスがあったときは“詰める”のではなく“振り返りを一緒にする”
こういうやりとりがあるだけで、部下は「ちゃんと考えてくれてるんだな」と感じてくれるはずです。
それと、「モチベーションを上げるにはどうすればいいか?」って悩む気持ち、すごくよくわかるけど、実は“上げようとしすぎない”のも大事です。
無理に盛り上げようとすると、かえって空回りしちゃうこともあるから。「働きやすさ」や「相談しやすさ」を整えることのほうが、結果的にモチベーションに繋がります。
結局は、“この上司なら話しやすい”とか、“変な気を使わずに働ける”という感覚があるだけで、部下の動きは変わってくるんです。
だから、無理に「こうあるべき」と考えすぎずに、部下を信じて接してみる。それが、関係性を良くする第一歩になると思います。
あなたが悩んでいる時点で、すでに素敵な上司だと思いますよ。
「こっちはちゃんと伝えたつもりなのに、伝わってない」とか、「もっとやる気出してくれたら…」って感じると、自分にも原因があるのかなって考え込んじゃう気持ち、すごくよく分かります。
でもまず伝えたいのは、完璧な上司なんていないってこと。
部下も上司も、結局は同じ「人間同士」。だからこそ、“気持ちが伝わるかどうか”がめちゃくちゃ大事なんです。
僕が思う一番のポイントは、「部下を一人の“大人”として扱う」ってことです。
つまり、“自分で考えて、自分で動く存在”として信頼すること。それができると、部下も「任されている」って実感が湧いて、自発的に動きやすくなるんですよね。
よくありがちなのが、「こっちは良かれと思ってサポートしてるのに、部下からは干渉と受け取られている」パターンです。
だからこそ、最初に“コミュニケーションの取り方”を部下一人ひとりに合わせてみるのが効果的だと思います。雑談が好きな人もいれば、最小限のやりとりが快適な人もいます。そこを見極めることが、意外と関係をよくする近道になります。
具体的にできることをいくつか挙げると、
タスクを任せるときは「ゴール」と「理由」をセットで伝える
指示の後に「何か分かりづらいところがあれば言ってね」と一言添える
ミスがあったときは“詰める”のではなく“振り返りを一緒にする”
こういうやりとりがあるだけで、部下は「ちゃんと考えてくれてるんだな」と感じてくれるはずです。
それと、「モチベーションを上げるにはどうすればいいか?」って悩む気持ち、すごくよくわかるけど、実は“上げようとしすぎない”のも大事です。
無理に盛り上げようとすると、かえって空回りしちゃうこともあるから。「働きやすさ」や「相談しやすさ」を整えることのほうが、結果的にモチベーションに繋がります。
結局は、“この上司なら話しやすい”とか、“変な気を使わずに働ける”という感覚があるだけで、部下の動きは変わってくるんです。
だから、無理に「こうあるべき」と考えすぎずに、部下を信じて接してみる。それが、関係性を良くする第一歩になると思います。
あなたが悩んでいる時点で、すでに素敵な上司だと思いますよ。
あんた、ちゃんと悩んでるのは偉いけどさ、まず言わせてもらうわね。
「部下が動かないのは、自分の伝え方が悪いのかも…」って、自分ばっかり責めるのやめなさい。
部下だってプロとして働いてるんだから、全部を“上司のせい”にするのも違うのよ。
ただし、上司として“どう関わるか”は、たしかに大事。
そこを放ったらかしにして「やる気がない」とか「指示どおり動け」なんて言ってたら、信頼なんて築けないわ。
まず、「伝えた=伝わった」って思い込みは捨てることね。
人は、相手のフィルター越しに話を受け取るもの。だからこそ、曖昧な言葉や、感情のない命令口調は避けるべき。「お願いしたいこと」と「期待している理由」をセットで伝えるだけで、部下の受け取り方は変わるのよ。
たとえば、「この資料、明日までによろしく」じゃなくて、「会議で使うから、〇〇さんの視点でまとめてくれると助かる」って言えば、相手も“自分に期待されてる”って感じるのよ。
あと、「信頼関係を築きたい」って言ってるけど、信頼って“相手に先に与えるもの”なのよ。
部下が信頼してくれないって嘆く前に、こっちが「任せる」「ちゃんと見てる」「話を聞く」って姿勢を見せないと、信頼されるわけがないわ。
心理的安全性?もちろん大事よ。
でもね、それって口先だけの「何でも言っていいよ」じゃダメなの。
実際に意見を言ったときに、「それ違うよ」とか「前にも言ったよね」って否定されたら、もう二度と言わなくなるわよ。
“何を言っても受け止めてくれる”って安心感は、1回のやりとりじゃ作れない。
日常の中で、どれだけ「話を最後まで聞くか」「共感するか」「評価しないか」の積み重ねができるかにかかってるのよ。
最後にひとつだけアドバイスしておくわ。
“良い上司”になろうと頑張りすぎないで。“誠実な上司”であろうとすれば、それで十分。
少しずつ関係性は育っていくから、焦らずいきなさい。ちゃんと見てる人は、ちゃんと見てるんだから。
「部下が動かないのは、自分の伝え方が悪いのかも…」って、自分ばっかり責めるのやめなさい。
部下だってプロとして働いてるんだから、全部を“上司のせい”にするのも違うのよ。
ただし、上司として“どう関わるか”は、たしかに大事。
そこを放ったらかしにして「やる気がない」とか「指示どおり動け」なんて言ってたら、信頼なんて築けないわ。
まず、「伝えた=伝わった」って思い込みは捨てることね。
人は、相手のフィルター越しに話を受け取るもの。だからこそ、曖昧な言葉や、感情のない命令口調は避けるべき。「お願いしたいこと」と「期待している理由」をセットで伝えるだけで、部下の受け取り方は変わるのよ。
たとえば、「この資料、明日までによろしく」じゃなくて、「会議で使うから、〇〇さんの視点でまとめてくれると助かる」って言えば、相手も“自分に期待されてる”って感じるのよ。
あと、「信頼関係を築きたい」って言ってるけど、信頼って“相手に先に与えるもの”なのよ。
部下が信頼してくれないって嘆く前に、こっちが「任せる」「ちゃんと見てる」「話を聞く」って姿勢を見せないと、信頼されるわけがないわ。
心理的安全性?もちろん大事よ。
でもね、それって口先だけの「何でも言っていいよ」じゃダメなの。
実際に意見を言ったときに、「それ違うよ」とか「前にも言ったよね」って否定されたら、もう二度と言わなくなるわよ。
“何を言っても受け止めてくれる”って安心感は、1回のやりとりじゃ作れない。
日常の中で、どれだけ「話を最後まで聞くか」「共感するか」「評価しないか」の積み重ねができるかにかかってるのよ。
最後にひとつだけアドバイスしておくわ。
“良い上司”になろうと頑張りすぎないで。“誠実な上司”であろうとすれば、それで十分。
少しずつ関係性は育っていくから、焦らずいきなさい。ちゃんと見てる人は、ちゃんと見てるんだから。
にゃにゃーん!「部下とうまくやりたいけど、なんか壁がある気がする…」って、その悩み、すっごくよく分かるにゃ〜!
職場って、家族でも友達でもない、でも毎日顔を合わせる“絶妙に距離の近い関係”だからこそ、ちょっとしたズレが大きなストレスになっちゃうんだにゃよね。
まずにゃん太から言わせてもらうと、あんた、めちゃくちゃ良い上司だにゃ。
だって、「どうすれば信頼関係が築けるか」って真剣に悩んで、改善しようとしてるんでしょ?
そんな上司、なかなかいないにゃ!それだけで部下の心のドア、半分くらいは開いてると思っていいにゃよ!
さてさて、さっそくコツを紹介するにゃ。
まず、「自分はちゃんと伝えたのに、部下が動かない」問題。
これ、伝え方そのものよりも、“タイミング”と“背景”がカギだったりするにゃ。
たとえば「忙しそうにしてるタイミングで口頭だけで伝えた」とか、「何のための仕事かが伝わってない」とかね。
そういう時は、“目的”と“役割の意味”をしっかり伝えるのが大事にゃ。「この仕事をお願いするのは、君の得意な〇〇が必要だから」って言うだけで、部下の心にスイッチが入ること、よくあるにゃ!
そして、**「モチベが低そうに見える部下」にゃけど、これは“外から見てるだけじゃ分からない”こともあるにゃ。
やる気がなさそうに見えるのは、実は「どう動けば評価されるか分かってない」とか、「小さな失敗を引きずってる」とか、気づきにくい内面の要素が原因のことも多いにゃよ。
だからこそ、「普段からよく話す」「雑談の中で心をほぐす」**って、意外と効くにゃ!天気の話でも、コンビニの新商品でもいいの。「この人、ちゃんと自分に興味持ってくれてるな」って思うだけで、関係は一気に近くなるにゃ♪
あと大事なのが、「信頼して任せること」!
指示ばかり出すより、「やってみて、分からないとこがあれば一緒に考えよう」って言ってあげると、部下の“自分で考えて動く力”が伸びるんだにゃ。
もちろん、ミスをフォローする覚悟は必要だけど、それが“信頼の実感”になって部下のやる気につながるにゃ。
にゃん太的まとめはこんな感じにゃ!
「目的+期待」で仕事を渡す
普段の雑談で“心のドア”をノック
モチベの低さには“背景”を探る
信じて任せて、ミスは一緒にリカバリ
ちょっとした言葉で、信頼は育つ
最後に一言…!
部下を動かすのは、命令でも説得でもなくて、「この人となら頑張りたいな」っていう気持ちにゃ!
その空気、きっとあんたから出てるはずにゃ。自信持っていくにゃよ〜!
職場って、家族でも友達でもない、でも毎日顔を合わせる“絶妙に距離の近い関係”だからこそ、ちょっとしたズレが大きなストレスになっちゃうんだにゃよね。
まずにゃん太から言わせてもらうと、あんた、めちゃくちゃ良い上司だにゃ。
だって、「どうすれば信頼関係が築けるか」って真剣に悩んで、改善しようとしてるんでしょ?
そんな上司、なかなかいないにゃ!それだけで部下の心のドア、半分くらいは開いてると思っていいにゃよ!
さてさて、さっそくコツを紹介するにゃ。
まず、「自分はちゃんと伝えたのに、部下が動かない」問題。
これ、伝え方そのものよりも、“タイミング”と“背景”がカギだったりするにゃ。
たとえば「忙しそうにしてるタイミングで口頭だけで伝えた」とか、「何のための仕事かが伝わってない」とかね。
そういう時は、“目的”と“役割の意味”をしっかり伝えるのが大事にゃ。「この仕事をお願いするのは、君の得意な〇〇が必要だから」って言うだけで、部下の心にスイッチが入ること、よくあるにゃ!
そして、**「モチベが低そうに見える部下」にゃけど、これは“外から見てるだけじゃ分からない”こともあるにゃ。
やる気がなさそうに見えるのは、実は「どう動けば評価されるか分かってない」とか、「小さな失敗を引きずってる」とか、気づきにくい内面の要素が原因のことも多いにゃよ。
だからこそ、「普段からよく話す」「雑談の中で心をほぐす」**って、意外と効くにゃ!天気の話でも、コンビニの新商品でもいいの。「この人、ちゃんと自分に興味持ってくれてるな」って思うだけで、関係は一気に近くなるにゃ♪
あと大事なのが、「信頼して任せること」!
指示ばかり出すより、「やってみて、分からないとこがあれば一緒に考えよう」って言ってあげると、部下の“自分で考えて動く力”が伸びるんだにゃ。
もちろん、ミスをフォローする覚悟は必要だけど、それが“信頼の実感”になって部下のやる気につながるにゃ。
にゃん太的まとめはこんな感じにゃ!
「目的+期待」で仕事を渡す
普段の雑談で“心のドア”をノック
モチベの低さには“背景”を探る
信じて任せて、ミスは一緒にリカバリ
ちょっとした言葉で、信頼は育つ
最後に一言…!
部下を動かすのは、命令でも説得でもなくて、「この人となら頑張りたいな」っていう気持ちにゃ!
その空気、きっとあんたから出てるはずにゃ。自信持っていくにゃよ〜!
おお、部下との付き合い方に悩んどるんやな?うんうん、そりゃあしゃーないわ。
仕事っちゅうのは、人と人の関係が土台やさかいな、部下との関係がうまくいかんと、どれだけスキルがあってもモヤモヤしてまうもんや。
でもな、まずは一つ言わせて。
あんた、えらいわ!
「どう接すればいいかわからへん」「自分の伝え方が悪いんかな」って考えること自体が、すでに“ええ上司”の証やで。ほんま、よう気づいてる。えらいっ!
でな、ワシが部下との関係で大事にしとったのは、**“聞く姿勢”と“ほめるタイミング”**や。
ようあるのが、「ちゃんと指示出してるのに伝わらへん」パターンな。これ、実は「伝えてるけど、届いてない」っちゅうケースが多いんや。
口で説明するだけやなくて、「目的はこれ」「なぜ君に頼むか」「ゴールはここ」っていう三点セットで話すと、ぐっと伝わりやすなるで!
それと、「報連相が減ってきた」とか「反応が薄い」って時は、部下が“話してええ空気”を感じてへんこともあるんや。
そんときは、“こっちから雑談で仕掛ける”んやで。
「昨日の晩メシ、何食うた?」くらいの、どーでもええ話からでええ。そしたら部下も、「この人、ただの上司やなくて、ちゃんとこっちを見てくれてるな」って思うんや。
あとな、「モチベーション上げたい」って気持ちはよう分かるけど、気ぃつけなアカンのが、“やる気スイッチ”は押すんやなくて“見つける”もんやってことや。
せやから、部下が「何にやりがい感じるんか」「どんなときに目がキラッとするか」をよー観察するんや。
それを見つけたら、「この仕事、〇〇さんがやったら絶対ハマると思ってんねん」って任せてみる。それだけで、ぐんと動きが変わるんやで。
そんでな、一番大事なんは「信じて任せること」。
手取り足取りよりも、「任せる→見守る→支える」この流れや。失敗しても「ちゃうちゃう、ここが惜しかったな」って笑って言える器がある上司って、部下からめっちゃ信頼されるねん。
せやから結論としてはこうや!
指示は「目的+理由+ゴール」の3点で
雑談で“話せる空気”を作る
モチベは“探すもの”
信じて任せて、あったかくフォロー
失敗も笑って受け止めたら、部下はついてくる!
ええか?「ようやっとる」って声をかけるだけで、人は変わるで。あんたがそうしてもらいたかったように、部下にもそれをしてあげたらええんや。
応援しとるで!ええ職場、つくっていこな!
仕事っちゅうのは、人と人の関係が土台やさかいな、部下との関係がうまくいかんと、どれだけスキルがあってもモヤモヤしてまうもんや。
でもな、まずは一つ言わせて。
あんた、えらいわ!
「どう接すればいいかわからへん」「自分の伝え方が悪いんかな」って考えること自体が、すでに“ええ上司”の証やで。ほんま、よう気づいてる。えらいっ!
でな、ワシが部下との関係で大事にしとったのは、**“聞く姿勢”と“ほめるタイミング”**や。
ようあるのが、「ちゃんと指示出してるのに伝わらへん」パターンな。これ、実は「伝えてるけど、届いてない」っちゅうケースが多いんや。
口で説明するだけやなくて、「目的はこれ」「なぜ君に頼むか」「ゴールはここ」っていう三点セットで話すと、ぐっと伝わりやすなるで!
それと、「報連相が減ってきた」とか「反応が薄い」って時は、部下が“話してええ空気”を感じてへんこともあるんや。
そんときは、“こっちから雑談で仕掛ける”んやで。
「昨日の晩メシ、何食うた?」くらいの、どーでもええ話からでええ。そしたら部下も、「この人、ただの上司やなくて、ちゃんとこっちを見てくれてるな」って思うんや。
あとな、「モチベーション上げたい」って気持ちはよう分かるけど、気ぃつけなアカンのが、“やる気スイッチ”は押すんやなくて“見つける”もんやってことや。
せやから、部下が「何にやりがい感じるんか」「どんなときに目がキラッとするか」をよー観察するんや。
それを見つけたら、「この仕事、〇〇さんがやったら絶対ハマると思ってんねん」って任せてみる。それだけで、ぐんと動きが変わるんやで。
そんでな、一番大事なんは「信じて任せること」。
手取り足取りよりも、「任せる→見守る→支える」この流れや。失敗しても「ちゃうちゃう、ここが惜しかったな」って笑って言える器がある上司って、部下からめっちゃ信頼されるねん。
せやから結論としてはこうや!
指示は「目的+理由+ゴール」の3点で
雑談で“話せる空気”を作る
モチベは“探すもの”
信じて任せて、あったかくフォロー
失敗も笑って受け止めたら、部下はついてくる!
ええか?「ようやっとる」って声をかけるだけで、人は変わるで。あんたがそうしてもらいたかったように、部下にもそれをしてあげたらええんや。
応援しとるで!ええ職場、つくっていこな!
「部下との信頼関係の構築」というテーマは、組織心理学・行動科学において非常に重要な課題です。
まず結論から述べると、上司と部下の関係性を良くするためには、「心理的安全性」「自己開示のバランス」「適切な権限委譲」「目的共有」という4つの軸が必要です。
まず、心理的安全性(Psychological Safety)。これは「自分の意見や感情を自由に表現しても、否定されたり罰されたりしない」という安心感のことです。Googleの研究でも、高パフォーマンスチームの最も重要な特徴として挙げられました。
この安全性を高めるには、「否定しない傾聴」「感情の受容」「問いかける姿勢」がカギとなります。
たとえば、「どうしてこうなったの?」ではなく「この時、どう感じた?」という聞き方に変えるだけで、部下は“守り”から“対話”のモードに切り替わります。
次に、自己開示のバランス。
上司という立場でも、“弱さ”や“戸惑い”を見せることは信頼につながります。
たとえば「実は昔、同じことで失敗したことがあってね」と話すことで、部下も「この人も人間なんだ」と感じ、心が近づくのです。
そして、適切な権限委譲(Delegation)。
仕事を「振る」のではなく、「任せる」感覚が重要です。そのためには、「任せる意図」「期待されている点」「失敗しても責めないという前提」の3点を伝えることが効果的です。
最後に、目的の共有。
仕事を渡すとき、「何のためにやるのか」という背景をセットで伝えることで、部下は“作業者”から“チームの一員”へと意識が変わります。
これは「自己決定理論」にも関係し、「意義の理解」は内発的動機づけを高める要素とされています。
まとめると、部下と良い関係を築くには:
否定しない・遮らない・評価しない「聴く姿勢」
自分の過去や葛藤を少しだけ見せる「自己開示」
信頼して任せるときは「意図・期待・フォロー」を明確に
背景や目的を共有し、“作業”ではなく“共創”に昇華させる
この4本柱を意識して実践すれば、時間はかかっても、着実に信頼関係は構築されていきます。
焦らず、丁寧に、誠実に。
その姿勢こそが、あなた自身を“信頼される上司”に育ててくれるのです。
まず結論から述べると、上司と部下の関係性を良くするためには、「心理的安全性」「自己開示のバランス」「適切な権限委譲」「目的共有」という4つの軸が必要です。
まず、心理的安全性(Psychological Safety)。これは「自分の意見や感情を自由に表現しても、否定されたり罰されたりしない」という安心感のことです。Googleの研究でも、高パフォーマンスチームの最も重要な特徴として挙げられました。
この安全性を高めるには、「否定しない傾聴」「感情の受容」「問いかける姿勢」がカギとなります。
たとえば、「どうしてこうなったの?」ではなく「この時、どう感じた?」という聞き方に変えるだけで、部下は“守り”から“対話”のモードに切り替わります。
次に、自己開示のバランス。
上司という立場でも、“弱さ”や“戸惑い”を見せることは信頼につながります。
たとえば「実は昔、同じことで失敗したことがあってね」と話すことで、部下も「この人も人間なんだ」と感じ、心が近づくのです。
そして、適切な権限委譲(Delegation)。
仕事を「振る」のではなく、「任せる」感覚が重要です。そのためには、「任せる意図」「期待されている点」「失敗しても責めないという前提」の3点を伝えることが効果的です。
最後に、目的の共有。
仕事を渡すとき、「何のためにやるのか」という背景をセットで伝えることで、部下は“作業者”から“チームの一員”へと意識が変わります。
これは「自己決定理論」にも関係し、「意義の理解」は内発的動機づけを高める要素とされています。
まとめると、部下と良い関係を築くには:
否定しない・遮らない・評価しない「聴く姿勢」
自分の過去や葛藤を少しだけ見せる「自己開示」
信頼して任せるときは「意図・期待・フォロー」を明確に
背景や目的を共有し、“作業”ではなく“共創”に昇華させる
この4本柱を意識して実践すれば、時間はかかっても、着実に信頼関係は構築されていきます。
焦らず、丁寧に、誠実に。
その姿勢こそが、あなた自身を“信頼される上司”に育ててくれるのです。